血清総蛋白執筆者:昭和大学病院医学部医学教育推進室教授 高木 康/昭和大学横浜市北部病院病院長 田口 進
肝臓や腎臓の異常、全身状態などを調べる検査です。低値でも高値でも、さらにくわしい検査を行います。
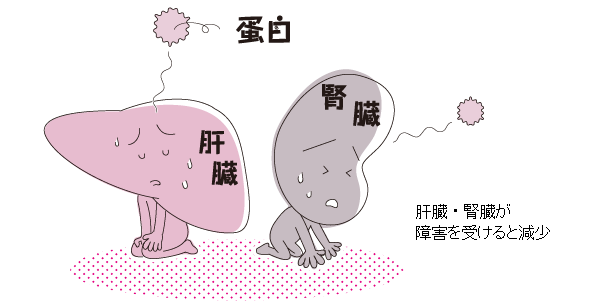
血清中に含まれている蛋白の総称。現在、100種以上の蛋白が知られており、そのうち最も多いのがアルブミン、ついで抗体活性をもつγ-グロブリン、ほかは微量。蛋白のほとんどは肝臓で合成され、人の健康を維持するためにさまざまな働きをしている。
血清総蛋白の基準値
6.5~8.0g/dl
肝機能・腎機能障害で低値に
血清蛋白の中で、最も多く存在するアルブミンは肝臓で合成されるため、肝機能障害の疑いがあるときは、まずこの検査を行います。肝臓の合成能力が低下するとアルブミンが減少し、血清中の総蛋白量は低下します。とくに慢性の肝臓病(慢性肝炎や肝硬変、肝臓がん)では、著しく低下します。
また、この検査は腎機能の障害を調べるときにも有用です。腎臓が障害されると、アルブミンをはじめとする蛋白が尿中に漏れ出てしまい、やはり血清中の総蛋白量は低下します。その代表的な病気がネフローゼ症候群です。
栄養状態、全身状態を把握する指標
血清蛋白の多くは肝臓でつくられて、その際にはアミノ酸をはじめとする種々の材料が必要になります。したがって、栄養状態の悪いときは、材料が不足して蛋白を合成することができなくなり、血清総蛋白は低下します。
また、何かの病気で口から食事がとれないと、1週間で2~4g/dl低下してしまいます。この検査をすると、栄養状態、全身状態が簡単にわかるため、とても重要な検査のひとつです。
検査当日の飲食は普通でよい
血清総蛋白は、蛋白に親和性のある(くっつきやすい)色素を用いた分析法によって測定されます。また、屈折計を用いて、大ざっぱな濃度を得ることも可能です。
基準値は6.5~8.0g/dlです。6.0g/dl以下なら低蛋白血症、8.5g/dl以上なら高蛋白血症とみなします。
検査当日の飲食は普通にとってかまいません。
低値でも高値でも再検査を
総蛋白は、低値でも高値でも何らかの異常を考え、さらにくわしい検査を行います。生理的要因(例えば、横になっての採血では座っての採血より10%程度低値になる)による低値の場合でも、再検査が必要です。
また、栄養不良による低値の場合は、急激な改善はみられないために1週間に1回程度の検査で十分です。
低蛋白の人は、高蛋白食を摂取して、蛋白源を十分補給する必要があります。
| おもな蛋白 | 機能 |
|---|---|
| アルブミン | 浸透圧維持、蛋白供給、各種物質の運搬 |
| α1-リポ蛋白 | コレステロールの運搬 |
| α1-抗トリプミン | 蛋白分解酵素(トリプシン、キモトリプシン)の阻害 |
| セルロプラスミン | 銅の運搬 |
| ハプトグロビン | ヘモグロビンと結合して尿中への排泄を阻止 |
| α2-マクログロビル | 蛋白分解酵素の阻害 |
| トランスフェリン | 鉄の運搬 |
| β-リポ蛋白 | 脂質の運搬 |
| フィブリノゲン | 血液凝固 |
| γ-グロブリン | 抗体活性 |
おすすめの記事
疑われるおもな病気などは

高値
慢性感染症、膠原(こうげん)病、多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症など

低値
肝機能障害、栄養不良、蛋白漏出(ネフローゼ症候群)など
- 出典:四訂版 病院で受ける検査がわかる本 2014年7月更新版