患者相談事例-181「単なる風邪だったのに、特定疾患療養管理料を取られたのはどうして?」
[患者さんの相談事例] 2017/03/10[金]
現代の医療現場では、自分なりの判断や意思決定が求められます。患者側にだって、治療パートナー(医療者)と上手に対話して、疑問解消・意思伝達できるコミュニケーションスキルがあった方が良いですね。
ここで紹介する「相談事例」は、患者側視点に基づくもので 、実際にはもっと実際にはもっと他の背景があったかもしれませんが、「私ならどうするか」を考えてみませんか?

単なる風邪だったのに、特定疾患療養管理料を取られたのはどうして?(42歳・女性)
 10歳の息子が風邪をひいて、38.5度に発熱、咳と鼻水もひどかったので受診することにしました。3年前からかかりつけにしていた小児科が先日閉院したため、以前かかったことのあるクリニックに3年ぶりに連れていきました。
10歳の息子が風邪をひいて、38.5度に発熱、咳と鼻水もひどかったので受診することにしました。3年前からかかりつけにしていた小児科が先日閉院したため、以前かかったことのあるクリニックに3年ぶりに連れていきました。
診察の結果、インフルエンザではなく、ふつうの風邪だと診断されました。診察が終わって会計で支払いをした際、領収書だけ渡されたので、「明細書も発行していただけますか?」と頼みました。すると明細書は出してくれたのですが、3年ぶりなのに再診料が請求されていて、「特定疾患療養管理料225点」と処方せんの加算も記入されていました。
そこで、会計窓口の人に「特定疾患療養管理料って何ですか?」と尋ねると、「直接先生に聞いてください」と言われて、診察室に通されたのです。ドクターは「咳に効く薬は喘息のときにも出す薬なので…」と言うので、「うちの息子は喘息ではないですよね? いままで風邪で咳止めを出してもらっただけで、管理料なんて請求されたことはありません」と言ったら、「何を請求するかは、それぞれの医療機関の判断ですから」と言い捨てて、診察室の奥へと入って行ってしまいました。どうにも納得がいきません。
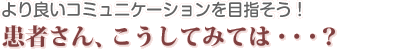
特定疾患療養管理料はいわゆる慢性疾患の患者の診療をおこなった際に、病状がコントロールできているか確認したり、薬や生活上のアドバイスや指導をしたりすることによって請求される管理料です。これを請求できるのは、かかりつけ医機能を持つ診療所か200床未満の病院で、診療所は225点、100床未満の病院は147点、100床以上200床未満の病院は87点と定められていて、月2回まで請求可能です。この管理料は初診で慢性疾患の診断をしてから1か月が経過しないと請求はできません。さらに、この管理料を請求している患者さんに薬を処方した場合には、院内処方だと処方料に、院外処方だと処方せん料に加算がつくことになっていて、この加算に限っては初診の際でも請求できることになっています。
厚生労働省の見解としては、患者側の判断で診療を打ち切って1か月経過すれば初診料を請求することは可能としています。しかし、どれだけ空いたら再診料を請求できないという決まりについて明記されたものはないと思います。
たしかに、単なる風邪なのに、慢性疾患扱いをして管理料を請求されるのは納得いかなくて当然と思います。上記のような情報を理解したうえで、改めてクリニックのドクターと話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
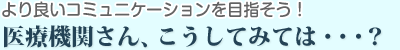
風邪の患児に出した咳止めが、喘息患者にも出すものだからと喘息扱いして特定疾患療養管理料を請求するというのは、やはり患者側の理解が得られる請求とは思えません。コスト意識を持った患者が増えてきているなか、明確に説明ができる請求のあり方が問われると思います。
※写真はイメージです
この実例紹介とアドバイスのご提供は・・・

認定NPO法人
ささえあい医療人権センターCOML
理事長 山口育子
- この記事を読んだ人は他にこんな記事も読んでいます。
記事の見出し、記事内容、およびリンク先の記事内容は株式会社QLifeの法人としての意見・見解を示すものではありません。
掲載されている記事や写真などの無断転載を禁じます。
掲載されている記事や写真などの無断転載を禁じます。