国立がん研究センター中央病院(東京都中央区)が名医に推薦されている分野
専門医より推薦を受けた診療科目・診療領域
国立がん研究センター中央病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。
このページでは、専門医より推薦を受けた分野(科目、領域)の特色や症例数、所属している医師について取材・調査回答書より記載しています。
※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
消化管内視鏡科
分野 |
消化器・一般内科 |
|---|---|
特色 |
消化管癌(食道、胃、大腸)の内視鏡治療に関しては常に日本のトップクラスの成績をあげており、世界中からの見学者や研修医も多く受け入れている。最近では東京医大より糸井隆夫准教授を非常勤スタッフとして招き、胆膵系の悪性疾患に対する診断・治療も行える体制となり、より充実した体制となっている。国立癌研究センター中央病院の最大の特徴は、外科、内科、放射線や病理などの各診療科との密接な連携の上で、治療方針を決めていくことであり、個々の症例においてそれぞれ最適な治療法を選択している。また内視鏡検診を併設するがん予防・検診研究センターにおいて実施しており、病院との緊密な連携を取っていることも大きな特徴である。 |
症例数 |
日本消化器内視鏡学会および日本消化器病学会の指導医・専門医である常勤の消化管内視鏡スタッフ医師7人およびがん予防・検診研究センター兼任医師3人を中心に、年間で約10,000件の上部内視鏡検査、3,000件の下部内視鏡検査、さらに100件の表在食道癌、400件の早期胃癌、600件の大腸腫瘍に対する内視鏡切除を行っている。色素内視鏡およびNBI(Narrow Band Imaging:狭帯域光観察)を用いた拡大内視鏡診断による正確な治療前診断のもと、年間約600件(食道60件、胃400件、大腸120件)の消化管ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)を実施している。 |
医療設備 |
高画質電子内視鏡システム(上部消化管、下部消化管)、超音波内視鏡システム、胆膵系電子内視鏡、カプセル内視鏡システム、ダブルバルーン小腸内視鏡システム、気管支内視鏡システム、CTほか。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ×
- 執刀医指名 ×
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
肝胆膵腫瘍科(肝胆膵内科)
分野 |
消化器・一般内科 |
|---|---|
特色 |
肝臓、胆道(胆嚢)、膵臓の癌に対する内科治療専門施設として、わが国最大の規模を有する。肝胆膵腫瘍科(肝胆膵内科+肝胆膵外科)をはじめ、放射線診断科、放射線治療科、精神腫瘍科などとともにグループ診療を実施している。 |
症例数 |
10年の入院患者数は491人で、主な疾患は、肝癌313人、膵癌143人、胆道癌35人である。各疾患に対する標準的治療をはじめ、病態や患者さんの希望により、数多くの臨床試験も実施している ★膵癌は病態により、①手術で切除可能(20%)、②手術で切除は不可能だが遠隔転移はない(30%)、③遠隔転移があり手術が不可能(50%)、に分けられる。当科では②と③の治療を担当しており、病状の軽減、QOL(生活の質)の向上を目指している。化学療法を中心に最先端の治療法を積極的に導入し、患者さんの状態やご希望に応じた治療や患者サポートを提供している ★切除不能な胆道癌に対しては、化学療法を中心に行っている。胆道癌、膵癌ともに、既存の抗癌剤に対する効果が一般的に不良であるため、新しい抗癌剤による臨床試験にも積極的に取り組んでいる ★肝臓癌に対しては病態に応じて、ラジオ波焼灼療法、経皮的エタノール注入療法、肝動脈塞栓療法、肝動注化学療法、全身性化学療法を実施している。ラジオ波焼灼療法・経皮的エタノール注入療法による5年生存率は約60%であり、手術療法に匹敵する成績を有している。 |
医療設備 |
MRI、CT、血管造影、血管造影下CT、核医学検査施設、放射線治療施設、PET、内視鏡検査施設、超音波検査施設など。相談支援センター、患者用図書室も設置。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
食道グループ・食道外科
分野 |
消化器・一般外科 |
|---|---|
特色 |
外科だけでなく内視鏡治療、抗癌剤治療、放射線治療の専門医とチームを組み、あらゆる病態に対して様々な治療法を組み合わせた治療を提供。拡大手術により根治を目指すだけでなく、化学放射線療法を受けた後の再発に対する難易度の高いサルベージ(救済)手術も積極的に引き受けている。 |
症例数 |
★10年実績・成績=年間食道切除手術症例128例。5年生存率(pTMN分類):I期79.7%、IIA期66.6%、IIB期60.7%、III期41.3%、IVA期32.2%、IVB期24.2%。治療の難しい食道癌に対して、集学的治療として多くの治療法を組み合わせることで治療成績を高める努力をしている ★国立がん研究センター中央病院では、食道外科・消化管内科・放射線治療科・消化管内視鏡科が食道グループとしてカンファレンスを合同で開き、全症例について診断と進行度に基づいた治療法の選択、新たな治療法の開発を行っている ★10年は他院での治療後の遺残再発の方を含む350人以上の新たな患者に、手術、内視鏡治療、化学放射線療法などの治療を行った。手術の標準術式は、切除によって得られる最大限の治療効果を目指すために、右開胸による3領域郭清としている。早期の症例に対しては胸腔鏡手術も導入している。進行例には手術前に抗癌剤治療を行い、その後に手術をすることで治療成績が向上している。手術をせずに食道を温存する根治的化学放射線療法も選択肢として提供し、治療後に遺残したり再発をした場合には手技的にきわめて難易度が高いサルベージ手術を行っている ★また、セカンドオピニオンを求めて受診される患者の予約も毎日受け付けている。様々な治療法を組み合わせることが多い食道癌の治療法について、患者によく説明し、納得して前向きに治療を受けてもらえるよう心がけている。 |
医療設備 |
MDCT、PET-CT、強度変調放射線治療。通院治療センター、相談支援センター。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
肝胆膵腫瘍外科グループ
分野 |
消化器・一般外科 |
|---|---|
特色 |
正確な術前画像診断、術中超音波診断、肝門阻血法、Pean鉗子による肝離断、系統的切除、術前門脈塞栓術、正確な術前残肝予備能評価、洗練された周術期管理、間欠式持続吸引による膵断端、吻合部ドレナージを行うことにより、安全な肝切除、膵切除を行う専門チーム。 |
症例数 |
当グループは肝胆膵外科手術を専門とし、07年には総手術数309例であった。初回手術例は肝癌47例、肝転移58例、肝内胆管癌11例、胆管癌31例、膵癌78例、十二指腸乳頭部癌16例、胆嚢癌11例であった。肝切除に関しては、胆道再建を伴う拡大肝葉切除は31例、肝膵同時切除2例、肝葉切除22例、肝区域切除16例、亜区域以下の部分切除が78例であった。膵頭十二指腸切除は72例、体尾部切除25例、分節膵切除5例、膵全摘5例で膵切除総数は108例であった。肝臓癌の5年生存率は80年から02年までの836例の症例でI:72.2%、II:65.8%、III:37.9%、IV:20.1%であった。通常型浸潤性膵癌では00年から04年までの168例で3年生存率はII:50%、III:61%、IV:39%であった。肝胆膵悪性疾患の治療は外科治療のみでは不十分で、放射線診断、IVR、肝胆膵抗癌治療グループとも綿密な連携をとり、総合的な治療を行っている。 |
医療設備 |
MDCT、MRI、腹部超音波、PET検査は各画像の専門医が診断を行う。高度な技術を要する経肝的胆管ドレナージ、門脈塞栓術(PTP)、経肝動脈的塞栓動注療法はIVRの専門医、RFAやエタノール注入は肝胆膵内科が行っている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 ×
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
大腸外科グループ
分野 |
消化器・一般外科 |
|---|---|
特色 |
直腸癌の手術は、排尿や性機能、肛門機能障害が大きな問題になるが、当科ではいち早く自律神経温存に取り組み、術後の後遺症を可能な限り軽減することで、患者さんのQOL(生活の質)の向上に努めている。 |
症例数 |
原発大腸癌手術件数は年間平均380例(うち直腸癌約200例)。腹腔鏡下腸切除は10年までに1,000例以上を経験している。現在、直腸癌の手術において当院では「自律神経温存術」は90%程度、「肛門括約筋温存術」は80%~90%の患者さんに適用し、術前同様の排尿機能や性機能が温存され、直腸癌術後のQOLは著しく向上している。また、従来は肛門括約筋温存が禁忌と考えられていた歯状線直上の病変に対しても、括約筋の一部を切除する手術法(intersphincteric resection:ISR)が行われている。ただし、肛門にできた癌や、高齢者で術後の負担が大きくなる時は、人工肛門を造設する。肛門温存にこだわることが必ずしも患者のQOLの向上につながらないケースもあると考える。腹腔鏡下腸切除は、早期癌、一部の進行癌に対して行うが、腫瘍の部位、進行度、また肥満や開腹歴、年齢などあるので適応を判断し行っている。 |
医療設備 |
MDCT、PET-CT、強度変調放射線治療、通院治療センター、相談支援センター。 |
- セカンドオピニオン受入 △
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
呼吸器腫瘍科(呼吸器内科)
分野 |
呼吸器内科 |
|---|---|
特色 |
日本の癌診療および研究の中枢施設であり、中央病院、東病院(千葉県柏市)の他、研究所、がん予防・検診研究センター、がん対策情報センター、臨床開発センターが併設されている。癌診療においては、現時点の最善の治療を提供するとともに、新しい治療法の開発のための臨床研究を積極的に実施している。外来診療は診断、内科、外科の3部門が「呼吸器科」として共同の診療体制をとり、患者さんの病状に合わせて診療を分担する。 |
症例数 |
呼吸器内科の年間新入院患者数は250~300人。肺癌の他、胸腺腫瘍、胸膜腫瘍などの胸部悪性腫瘍に対して、抗癌剤による化学療法や放射線治療を併用した化学放射線療法など、標準的あるいは最新の治療を実施している。新しい治療法の開発は、当センターの最大の使命であり、新治療法の臨床試験や新薬の治験に、積極的に取り組んでいる。患者さんには病状をありのままにお話し、選択肢となる各治療法を説明して十分話し合ったうえで、個々の患者さんにとって最適の治療方針を決定する。また、患者さんの病状に合わせ、居住地域の基幹病院や緩和ケア専門施設と連携体制をとり、診療にあたっている。 |
医療設備 |
CT、MRI、PET、マイクロトロンなど。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
眼腫瘍科
分野 |
眼科 |
|---|---|
特色 |
がん専門病院として、眼部腫瘍性疾患(悪性および良性腫瘍、腫瘍との鑑別を要する疾患)を対象として診療している。また、他臓器腫瘍の治療に付随する眼科的合併症の診療も行っている。一般的な白内障、緑内障、網膜剥離などは、原則として扱っていない。 |
症例数 |
10年度の初診患者数は約150人、全例が眼部腫瘍性疾患。網膜芽細胞腫44例、脈絡膜悪性黒色腫16例、眼瞼腫瘍14例、眼窩腫瘍18例、結膜腫瘍18例など。年間総手術件数は約300件、全例が腫瘍関連の手術であり、90%以上を全身麻酔で行った ★網膜芽細胞腫は、適応があれば眼球保存治療を行っている。腫瘍の進行度により全身化学療法、レーザー治療、小線源治療などに加え、局所化学療法を組み合わせて治療を行っている。眼球温存率は国際分類A~C群で90%、D群で50%、E群で約10%である ★脈絡膜悪性黒色腫は、腫瘍の大きさにより小線源治療、粒子線治療、眼球摘出のいずれかを選択している。小線源治療は現在当院でしか行うことができない。小線源治療は腫瘍厚5mm程度までが適応であり、眼球保存率は80%程度である ★眼瞼・眼窩・結膜腫瘍は、手術治療を標準治療として行っているが、症例により放射線治療も積極的に行っている。 |
医療設備 |
超音波画像診断装置、超音波生体顕微鏡、螢光眼底カメラ、ダイオードレーザー、冷凍凝固、放射性小線源治療設備。全身検査としてCT、MRI、核医学検査、PET-CT。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
血液腫瘍科
分野 |
血液内科 |
|---|---|
特色 |
造血器腫瘍に対する標準的治療の実践と、最善の治療体系を確立するための臨床試験を行っている。開発的診断、治療研究によって治療成績の壁の打破を目指す。移植が必要な場合は幹細胞移植科で行う。グループ内で統一した方針で治療が行われ、入院患者さんだけではなく、外来通院の患者さんについても診療グループとしての方針が貫かれている。レジデント、チーフレジデント、スタッフでチームを組み、さらに全体のカンファレンスで最終決定しており、治療選択がずれないように診療している。過去においてはATL(成人T細胞リンパ腫)、MALTリンパ腫などの疾患概念の確立に貢献した。 |
症例数 |
悪性リンパ腫の年間新患者数の約300人は国内最多である。白血病の新患者数は約80例。多発性骨髄腫は10例程度である。日本で行われるこれらの分野での新薬の臨床試験のほとんどを行っている。骨髄異形成症候群に対する新薬治験も実施中である。標準的治療法が確立されている場合には、その治療法を確実に行う。確立されていない場合には、当院で可能な治験薬を含んだ臨床試験への参加をお勧めする。造血幹細胞の適応については、幹細胞移植科との合同のカンファレンスで検討している。治療方針の決定に重要な細胞表面マーカー検索や腫瘍細胞の遺伝子検索も院内の検査部で行っている。JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)および、JALSG(日本成人白血病研究グループ)の中核的な施設であり、プロトコールの治療計画の立案から参画し、指導的役割を果たしている。 |
医療設備 |
無菌室7。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
脳脊髄腫瘍科
分野 |
脳神経外科 |
|---|---|
特色 |
脳腫瘍、特に悪性脳腫瘍を対象として治療を行っている。エビデンス(科学的根拠)に基づいた手術、放射線治療、化学療法を行う一方、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)の脳腫瘍部門の代表施設として、全国レベルでの臨床試験を実施し、新規治療法の開発に努めている。 |
症例数 |
年間延べ入院数は300〜350人、大半が悪性脳腫瘍患者であり、手術目的のみでなく、化学療法目的の入院も多い ★手術件数は、神経膠腫30〜40例、転移性脳腫瘍30〜40例、髄膜腫10〜20例、悪性リンパ腫10〜15例、上記以外の脳腫瘍20例などで、合計120〜140例。このうち、開頭による腫瘍摘出は100例、局所麻酔による生検術10例、オンマヤ貯留槽設置術10例、V-Pシャント5例、その他10例程度で、開頭による脳腫瘍摘出件数は国内でも有数である。開頭手術には全例において術中ナビゲーションシステムを用いて腫瘍の位置確認し、運動野付近の手術では誘発電位にて運動野を同定、さらに覚醒下手術も行い、手術による神経症状の悪化を防いでいる ★悪性腫瘍については、放射線治療部医師と照射部位、線量を検討しながら放射線照射を行っている。95年以降の悪性脳腫瘍の治療成績は膠芽腫の5年生存率11.9%、退形成性星細胞腫34.3%であり、いずれも脳腫瘍全国統計の7%、23%を上回っている。国内最大の多施設共同臨床試験クループJCOGの脳腫瘍部門代表施設として臨床試験を実施している。現在、悪性神経膠腫に対する第2相試験(ACNUとACNU+procarbazineとの比較試験)を終了し、現在、膠芽腫に対する術後放射線治療+TMZと放射線治療+TMZ+INF-βのランダム化第2相試験を実施中である。また、転移性脳腫瘍に関しては、手術後の全脳照射と定位照射との第3相比較試験を行っている。いずれも国内での悪性脳腫瘍に対する標準治療を確立することを目的とし、全国の37の脳神経外科施設の協力を得て実施している。 |
医療設備 |
MRI、CT、PET、DSA、術中ナビゲーションシステム、手術用超音波吸引装置、術中超音波、神経モニタリング装置、神経内視鏡、放射線治療装置。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
乳腺腫瘍科
分野 |
乳腺・内分泌外科 |
|---|---|
特色 |
当院は、乳癌治療を専門とする乳腺外科、腫瘍内科、放射腺科、病理、形成外科などの多くの部門の医師と看護部門(乳癌看護認定看護師2人)、あるいは診断治療に携わる技師や薬剤部などが協力しあうチーム医療にて、最善の医療を乳癌患者さんに提供することを目標としている ★診断においては、MRI・CT・乳腺エコー・マンモグラフィ・PET-CTなど、各種の画像検査による良性・悪性あるいは癌の広がり診断を行い、それに対する細胞診・針生検・マンモトーム生検などを駆使することにより確定診断を下し、患者さん個々にあった治療方針の決定を行っている。また、他院にて診断が難渋した患者さんや超早期の乳癌患者さんも放射線診断部と連携して的確に診断を下している ★毎週の手術症例を乳腺外科、腫瘍内科、放射線診断部、検査部と合同カンファレンスを行い、手術方法の決定を行っている。術前・術後・再発後の全身療法に対しても、最新のエビデンス(科学的根拠)をもとに7人の腫瘍内科医と外科医が協力して最善の薬物療法を決定している。当院は手術前の化学療法やホルモン療法を積極的に導入し、乳房温存手術が困難な症例に対してもその効果により、多くの症例で乳房温存手術を可能としている。術後は再発のリスクに応じて、最新のエビデンスに基づいて作成された乳腺グループ診療ガイドラインに沿って、積極的に術後補助薬物療法を導入している。これらの薬物療法(化学療法)は、外来通院治療センターにて副作用を熟知した専門の腫瘍内科医により安全に実施されている。また、放射線治療は専門医による精度の高い副作用の少ない治療が可能となっており、照射期間を短縮した治療や非照射治療も臨床試験として実施している ★当院の治療の主要な課題である手術低侵襲化に関しては、センチネルリンパ節生検を高度先進医療として先駆けて実施し、現在では非手術療法であるラジオ波熱凝固療法を高度医療として臨床試験を行っている ★乳癌術後のケアは重要であり、地域のクリニックの先生と医療連携も行い、治療後も地元でも安心して過ごせるように情報交換を行っている。当院の患者さんは、東京、関東ばかりでなく、北は北海道から南は沖縄さらには海外からも診断、治療、セカンドオピニオンを希望して来院するため、地域との連携は今後さらに重要になるものと考える ★癌に伴う精神的な悩みに関しては、腫瘍精神科医が相談にのり、癌や治療に伴う疼痛に対しては痛みの専門外来にて緩和ケアチームが対応し、リンパ浮腫外来も設置している。このようなチーム医療によって、総合的にすべての病期の乳癌患者さんを診療することが可能となっている。また多くの臨床試験や治験を実施し、標準治療の確立と新しい治療法・診断の開発にも力を入れており、最新のエビデンスに基づいた診療を行っている。 |
症例数 |
治験は乳腺外科と乳腺内科をあわせ約20のプロトコールを行っている。手術症例数は乳癌の罹患率の上昇に伴い、07年度は575症例となっている。大きな腫瘍の患者さんが適応になる術前治療は約20%の患者さんに行い。約85%の患者さんに治療効果(腫瘍の縮小)を認め、さらに術前化学療法を行った60%の患者さんに乳房温存療法を行い、顕微鏡の検査で16%に癌細胞の消失が確認された ★治療=乳房温存手術は60%、乳房全摘手術は40%(手術中に切除断端陽性のために乳房温存手術から乳房全摘への変更も含む)・センチネルリンパ節生検は全手術症例の70%に行い、そのうちの83%の患者さんは腋窩リンパ節が温存されている。手術の低侵襲化の実現により、これらの患者さんの入院期間は平均3~4日にまで短縮されてきている ★病期別治療成績(10年生存率)=病期0:100%、I:97%、II:87%、IIIa:78%、IIIb:64%、IV:55%である。初発乳癌の取り扱い数は575例(07年度乳腺外科初診)、初発病期IVは21例(腫瘍内科初診)。治験実施数(23件、07年度)。 |
医療設備 |
MRI、CT、乳腺エコー、MMG、PET-CT、放射線治療機器など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
緩和ケア外来
分野 |
緩和ケア |
|---|---|
特色 |
癌の苦痛からの解放という視点から、癌の痛みのほか息苦しさ、倦怠感、吐き気や食欲不振など様々な症状緩和治療を行っている。緩和ケア外来で対象とする痛みは、癌自体による痛みのほか癌に関連するあらゆる手術後の痛みや化学療法などに伴う痛みやしびれ、帯状疱疹後神経痛なども対象にしており、地域の総合病院や診療所との連携治療も行っている。入院中に緩和ケアチームが診療を行った患者さん(年間350人)についても退院後のサポートを行っている。痛みの治療に当たっては、整形外科、放射線治療部、放射線診断部など他の専門領域との協力体制による治療も多く実施しており、薬剤による治療に加えて患者さんごとの痛みの原因に合わせた治療を組み合わせている。また、高度の専門性を必要とする神経ブロックや、脊髄鎮痛法に精通したスタッフによる治療のほか、臨床試験を含む新たな鎮痛治療の開発にも取り組んでいる。患者さんに加えてご家族へのケアという視点から、精神腫瘍科や相談支援センター(ソーシャルワーカー)との連携体制も充実しており、不眠や気分の落ち込み、社会生活や今後の療養に関する不安など多くの癌患者さんやご家族が経験する様々な困難に幅広く対応している。 |
症例数 |
外来患者数は年間908人、医療用麻薬などの鎮痛薬による治療約73.7%、鎮痛補助薬などの特殊な薬剤による治療約57.9% ★外来への依頼目的:痛み97.4%、しびれ31.6%、息苦しさ2.6%、その他3%(重複あり) ★癌の種類:肺癌24%、乳癌24%、直腸癌、悪性リンパ腫8%、白血病・悪性中皮腫5%、その他(年間1症例程度の癌腫)26% ★癌治療と並行して痛みの治療を行っている患者さんの割合:39.5%、(術後痛への対処:21%)。基本的には当院で癌治療実施中または経過観察を受けている患者さんを対象にしている。現在他院で受けている緩和ケアや痛みの治療に対するセカンドオピニオンの希望には対応可能。 |
医療設備 |
キセノンレーザー、鍼灸治療(入院中の患者さんが対象、緩和治療実施中に医師が必要と認めた場合にのみ実施)。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
国立がん研究センター中央病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
国立がん研究センター中央病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 名医の推薦分野について
- 名医の推薦分野に掲載する情報は、ライフ企画が独自に調査、取材し、出版する書籍、「医者がすすめる専門病院」「専門医が選んだ★印ホームドクター」から転載するものです。出版時期は、それぞれの情報ごとに記載しています。全ての情報は法人としてのQLifeの見解を示すものではなく、内容を完全に保証するものではありません。
 QLife会員になると特典多数!
QLife会員になると特典多数!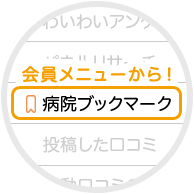


50代以上女性 2016年01月12日投稿
骨シンチ検査、前日の晩から眠れないくらい怖かった。 顔の直前までカメラが迫ってくるという書き込みを見てしまって、検査台に乗った時点で足がガクガク震えてた。 でも、でも、…続きをみる