日本医科大学付属病院(東京都文京区)が名医に推薦されている分野
専門医より推薦を受けた診療科目・診療領域
日本医科大学付属病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。
このページでは、専門医より推薦を受けた分野(科目、領域)の特色や症例数、所属している医師について取材・調査回答書より記載しています。
※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
消化器内科
分野 |
消化器・一般内科 |
|---|---|
特色 |
我が国における消化器内視鏡診断・治療学の草分けである常岡健二元学長の就任後、68年には世界に先駆けて内視鏡的胃ポリープ切除術を行うなど、消化器病学の進歩に貢献してきた伝統ある消化器内科である。患者の立場に立った心の通った医療を理念とし、食道、胃・十二指腸、小腸・大腸、肝胆膵の4部門が個々に外科、放射線科など他の診療科と随時カンファレンスを行い、全診療科連携による集学的診療を目指している。また内視鏡センターに常勤医を3人配置し、吐下血など緊急内視鏡検査が必要な疾患に対して常時迅速な対応が可能である。 |
症例数 |
10年診療実績:外来患者数約30,000人、入院患者数約700人(常時50人以上)。内視鏡検査:上部消化管約5,000例(うち経鼻内視鏡600例)、下部消化管約2,000例、胆道膵臓約100例 ★食道疾患=我が国唯一の21チャンネル高解像度食道内圧測定器を用いた胸やけ、嚥下困難を主症状とする食道運動機能異常の診断が特色である。また食道アカラシアに対するバルーン噴門部拡張術を積極的に実施しており、10年の症例数は15例であった。食道癌に対しては他科との協議を通して手術、内視鏡的切除術、放射線療法、化学療法を適宜組み合わせ、病態に合わせた集学的治療を行っている ★胃・十二指腸疾患=年間150例を超える重症出血患者に対して内視鏡的止血術を施行し、救命に貢献している。ヘリコバクター・ピロリ菌感染症例に対する除菌療法の成功率は約80%、除菌失敗例に対する2次除菌も約80%の高い奏効率を得ている。胃癌に対する内視鏡的胃粘膜一括切除術(ESD)を積極的に行っており、10年の症例数は約65例であった。また外科的手術不能例には病態、患者の状態に合わせた化学療法を行い、胃原発MALTリンパ腫については血液内科、消化器外科と緊密に連携し、最善の治療法を選択している ★小腸・大腸疾患=大腸癌、腺腫に対する内視鏡的切除術を年間約400例施行している。03年より導入したダブルバルーン小腸内視鏡検査法は年間100例前後施行しており、カプセル内視鏡検査の併用で診断困難な消化管出血・小腸病変の診断治療に画期的な成果をあげている。潰瘍性大腸炎、クローン病など炎症性腸疾患については従来の治療法に加えモノクローナル抗体治療、白血球除去療法などを取り入れ、集学的治療を行っている。下部消化管出血性疾患、腸閉塞など緊急疾患については専門医が迅速に対応できる体制を整えている ★肝胆膵疾患=入院患者の約60%を占め、その約60%が慢性肝疾患、肝癌症例である。肝癌については進行度、予備能を考慮し、外科と連携して治療選択を行っている。経皮的ラジオ波熱凝固療法(RFA)は年間約60例行っており、肝動脈塞栓療法(TACE)と組み合わせて最大の治療効果が得られるように工夫している。また切除不能、局所治療不能の進行症例については肝動注化学療法も行っている。肝硬変に合併する腹水、食道胃静脈瘤、肝性脳症に対して門脈血行動態の解析に基づいて、薬物療法、内視鏡的治療、カテーテル治療の中から病態に則した治療法を選択している。また、難治性腹水、難治性食道静脈瘤に対して、高度先進医療として経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術(TIPS)を行っており、特に薬物療法で改善しない難治性腹水に対し、半年間の観察では約75%に改善を得ている。94年の導入以来、約170例と東日本では最多の症例経験を有する施設である。B型、C型慢性肝炎に対してはエビデンス(科学的根拠)に基づいたインターフェロン、内服薬併用療法を行っており、治療終了後も専門医によるきめ細かい経過観察を心がけている。重症急性肝炎、肝不全症例に対しては集中治療室、移植外科と連携し、あらゆる病態に備えた迅速な治療に配慮している。胆膵疾患では胆石症、胆嚢炎、胆道癌、急性膵炎、膵嚢胞腺腫および膵癌について、内視鏡的各種処置を適切に実施するとともに、切除不能の悪性腫瘍症例については積極的に外来化学療法を導入している。 |
医療設備 |
CT、MRI、電子ファイバースコープ(上部消化管、小腸、下部消化管、胆道膵管)、超音波内視鏡、超音波・カラードプラ超音波装置、カプセル内視鏡解析設備、ラジオ波熱凝固装置、回転血管造影装置、21チャンネル高解像度食道内圧測定器など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
分野 |
消化器・一般外科 |
|---|---|
特色 |
本院は08年4月にがん診療連携拠点病院としての指定を受けているが、なかでも当科は消化器外科領域を中心に5大癌のうちの4疾患(胃癌、大腸癌、肝癌、乳癌)を扱う診療科である。癌診療を中心にした連携拠点病院として、地域医療を担当される病院・診療所との緊密な連携を保ちながら、常に患者さんの立場を考えた丁寧な医療を心掛けている。外来担当医は各々の専門分野を持っているが、専門外の疾患についても幅広い臨床経験を有しており、救急を含む様々な病態に積極的な対応が可能である。さらに、近隣の先生方から曜日の制約なくご紹介頂けるように、毎日の外来診療を消化器における各臓器の専門医が担当し診療体制の充実を図っている。また、癌診療だけでなく胆石・胆嚢炎、腸閉塞や急性腹症、肝硬変から食道静脈瘤、門脈圧亢進症など種々の良性疾患の治療にも精通しており、初診から検査および手術を含む治療について、そのおおよそのスケジュールを提示するよう努めている。単一診療科として、同一教育システムのもとで専門スタッフがそれぞれの疾患に従事しており、縦横の連携もスムーズである。近年とくに増加傾向である多臓器疾患を抱えた症例に対しては、総合力で対応できる消化器外科部門である。 |
症例数 |
年間手術患者は約1,000件以上(08年1,033件、09年1,044件、10年1,140件)であり、その大部分にクリニカルパスに沿った治療を施行している ★また、内視鏡・腹腔鏡を屈指した治療を積極的に取り入れ、「からだにやさしい手術(低侵襲手術)」をすべての臓器に適応しており、その疾患に最適な標準治療を同一診療機関で提供できる。一方、高齢化に伴う種々の基礎疾患(合併症)によって手術困難と判断される病態も少なくないが、当科では大学付属病院・特定機能病院かつがん診療拠点病院として総力をあげて治療に取り組んでいる ★さらに「治療」だけでなく「診断」も重要な日常診療となっており、内視鏡センターでは年間約7,000件の上部内視鏡検査による診断および内視鏡的治療(胃癌78例、食道癌16例)を行っている ★年間手術の内訳は胃癌(135例)、大腸癌(182例)、肝癌(71例)、食道、肝胆膵癌および良性疾患などとなっているが、腹腔鏡などの内視鏡を利用した腹腔鏡下手術(食道癌10例、胃癌70例、大腸癌97例、原発性・転移性肝癌7例、食道良性疾患10例、胆石91例、膵・脾・副腎30例、虫垂炎15例、ヘルニア修復5例など)を積極的に取り入れている ★また、主に胃癌(年間450件)、大腸癌(500件)、膵癌(300件)、乳癌(1,800件)に対する抗癌剤治療などの化学療法を、外来輸液療法室にて施行することで、QOL(生活の質)を重視した集学的治療を志している ★当教室の伝統である、『徒らに成績などの数字に惑わされることなく、患者さんが最も必要としている「満足」を提供できるような十分な診断および治療法の提示、セカンドオピニオンの勧め』を忘れず、全人的診療を心掛けている。 |
医療設備 |
PET、MRI、ヘリカルCT、血管造影装置、内視鏡装置(経鼻およびNBI)、放射線治療照射装置、ラジオ波およびマイクロターゼ焼却装置他。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
呼吸器内科
分野 |
呼吸器内科 |
|---|---|
特色 |
すべての呼吸器疾患に対応できる診療体制を整えている。特に肺癌については弦間教授を中心に、「地域がん診療連携拠点病院」として高度医療を行っている。慢性気道感染・びまん性肺疾患については、吾妻教授、斉藤講師らが対応し、慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息・睡眠時無呼吸症候群、慢性呼吸不全については木田教授グループが対応している。この領域の外来診療は市ヶ谷に呼吸ケアクリニック(03-5276-2325)という専門施設を整備し、患者サイドの利便性を高めている。このような体制のもと、以下のようなトップレベルの呼吸器診療を行っている。 |
症例数 |
年間外来患者数は44,000人(呼吸ケアクリニック含む)、入院患者数は延べ24,000人。症例の内訳は、腫瘍(肺がん、縦隔腫瘍など)、呼吸器感染症(肺炎、胸膜炎、肺結核、非結核性抗酸菌症、肺真菌症など)、気管支喘息、慢性気道感染(気管支拡張症など)、びまん性肺疾患(間質性肺炎・肺線維症、膠原病肺、塵肺症、過敏性肺炎、サルコイドーシスなど)、COPD(肺気腫、慢性気管支炎)、気胸、肺循環障害など、呼吸器疾患領域全体を網羅している。なお在宅酸素療法、同人工呼吸療法は主に呼吸ケアクリニックで対応している ★肺癌の診断と治療=肺癌治療の専門施設として定評を得、入院患者の約8割が肺癌治療目的であり、関東一円の広い範囲からの受診が多い。肺癌の手術適応は、当院呼吸器外科と詳細な検討の後、治療方針が決定される。侵襲の少ない胸腔鏡手術を積極的に取り入れているのも当院の特徴と言える。当科は各種併用化学療法の開発、副作用対策などについて多くの実績をもっており、標準治療はもとより、後述のような新しい治療法も積極的に行っている。ポストヒトゲノム時代に対応し、遺伝子解析を行い個々の腫瘍や体質を詳しく解析して、化学療法前に有効性や副作用の推定を行い、各症例に最適と考えられる薬剤を使用する個別化治療も実施している。間質性肺炎、COPDなど合併症のある肺癌治療には、幅広い診療体制が必須であり、この分野の新しい試みを行っている。また、可能な限り就労しながら、日常生活に支障なく治療を継続することを目的に、専用の治療室を用いた外来化学療法を行っている。緩和ケアについても積極的に取り組み、がん診療連携拠点病院の中心としてその責任を果たしている ★慢性気道感染・びまん性肺疾患の診断と治療=マクロライド少量長期療法により、びまん性汎細気管支炎の予後は明らかに改善した。現在は、長年にわたる近縁疾患の難治性の慢性気道感染症(気管支拡張症など)の新しい治療法の開発に取り組んでいる。当科ではびまん性肺疾患症例に対し、高分解能CT、気管支肺胞洗浄、経気管支的肺生検、必要に応じて呼吸器外科の協力を得て胸腔鏡下肺生検を行い、正しい診断に基づきレベルの高い治療を行っている。特に間質性肺炎については多くの臨床実績がある。特発性肺線維症に対しては、新薬の治験を含めて積極的な治療に取り組んでいる。急性呼吸不全の治療は、PMXを用いた先進治療や、高度救急救命センターや集中治療室と連携した高度医療を実現している。また、サルコイドーシスについては、眼科、循環器内科と合同で全身的管理が行える体制を整えている ★慢性閉塞性肺疾患、睡眠時無呼吸症候群の診断と治療=気管支喘息、COPD、睡眠時無呼吸症候群は、木田教授を中心とする医療チームが専門性の高い医療を行っている。特にセルフマネジメント(自己管理)を強くするために指導、教育は斯界でも高く評価されている。呼吸ケアクリニック(TEL 03-5276-2325)は03年12月に開院以来、受診者の総数は6,000人を超え、北海道、九州を含むほぼ全国からの受診がある。別稿を参照。 |
医療設備 |
X線(単純、ヘリカルCTなど)、MRI、核医学検査、気管支ファイバースコープ、超音波気管支鏡、ビデオ観察機器、レーザー治療機器、ポリソムノグラフィー、呼吸機能検査、胸腔鏡、リニアック。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ×
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
循環器内科
分野 |
循環器科 |
|---|---|
特色 |
循環器領域のどのような疾患に対しても、それぞれの専門家によるスピーディーで適切な対応が可能である。特に迅速な対応が求められる重症心疾患に対しては、外来から集中治療室(CCU)、麻酔科、放射線科、再生医療科、心臓血管外科までのスムーズな協力体制の下に最新で最善の治療を行っている。急性心筋梗塞、不安定狭心症、難治性心不全の治療はCCUを中心に行い、カテーテルインターベンション、心臓バイパス手術、補助循環療法、心臓再同期療法などの治療を行っている。解離性大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、肺動脈血栓塞栓症など重症血管病変に対しても診断からカテーテル治療、血管再生療法、手術まで即座に対応している。心房細動、心房頻拍、心室頻拍など難治性頻脈性不整脈に対してもカテーテル治療が可能となり成果をあげている。卒煙外来など時代にマッチした特殊外来もあり、実績をあげている。 |
症例数 |
年々増加する循環器疾患患者数を反映して、日本医科大学付属病院の平均1日外来受診者約2,000人のうち、循環器内科に来院する患者は1日平均200人近くに達している。また、病院の定床数1,002床のうち集中治療室17床、循環器内科50床があり、循環器内科への年間入院患者数約1,630人の平均在院日数は約18日と年々短縮傾向にある。これは早期発見、早期治療の成果である。集中治療室への入院は年間870件、そのうち急性心筋梗塞136件あり、重症心不全約150件、解離性動脈瘤約20件であり、救急治療→一般病棟→リハビリテーション→外来へと病期に応じて専門スタッフが的確な治療を行っている ★生理機能検査室で実施される心電図は年間30,000件、ホルター心電図3,630件、心臓超音波検査8,804件、ドブタミン負荷心エコー199件、経食道心エコー355件に達するが、多くの検査予約は1週間以内に実施可能である。緊急性が高い場合は、当日実施している。心臓リハビリテーションは年間2,124件、運動負荷試験1,205件、心肺運動負荷試験150件、放射線科の協力の下に負荷心筋シンチグラムは279件施行している ★高い技術と専門性を要求されるカテーテルインターベンション治療のために、専門スタッフが24時間体制で対応している。冠動脈造影検査は年間1,000件、カテーテルインターベンション350件(バルーン拡張術のみ16件、ステント拡張術326件、ロータブレーター8件)で、成功率97%ときわめて良好な成績をあげている。閉塞性肥大型心筋症に対する経皮的中隔心筋焼灼術は30件と、国内でトップレベルの実績がある。僧房弁狭窄症や大動脈弁狭窄症など、重症弁膜症に対するカテーテル治療も行っている。放射線科で行う心臓マルチスライスCT検査により、非侵襲的に冠動脈病変の評価が可能となった ★不整脈診断に必要な電気生理学的検査は年間200件、そのうちカテーテルアブレーション172件(心房細動、心房粗動および心房頻拍、発作性上室性頻拍、心室頻拍)を行っている。近年増加傾向にあり、治療困難とされてきた心房細動に対しても積極的にカテーテルアブレーションを行っており、アブレーション後、抗不整脈薬なしで心房細動の再発なしが57%、薬剤内服により再発なしが38%と、良好な成績を収めている。心臓血管外科で施行したペースメーカー植え込み症例は年間で新規44件、ジェネレーター交換27件、また植え込み型除細動器26件、交換10件、心臓再同期療法ペースメーカー植え込みは42件となっている。 |
医療設備 |
ホルター心電図、カルジオフォン、心臓超音波装置、トレッドミル、エルゴメーター、head up tilt検査、CT、マルチスライスCT、MRI、心臓カテーテル検査室など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
心臓血管外科
分野 |
心臓血管外科 |
|---|---|
特色 |
当院における心臓血管外科手術は72年から開始され、30年以上の歴史を有する。03年6月より心臓血管外科として独立した診療科となった。90年代より手術数は飛躍的に増加し、それに伴い手術成績も非常に良好となっている。症例は学内のみならず都内・近県の諸施設からの紹介も多い。当院には我が国の救急医療をリードする高度救命救急センターに加えて、都内でも有数のベッド数19床を誇る心疾患集中治療室(CCU)があり、虚血性心疾患、心不全、急性大動脈解離、その他循環器疾患の診療を24時間体制で行っている。当院CCUの特徴は、循環器内科・心臓血管外科・麻酔科が合同で診療体制を組み、各科の連携が非常に密接なことである。従って冠動脈外科手術や大血管手術などの緊急手術への対応は迅速で、手術成績は満足すべきものである。10年より東京都の急性大動脈スーパーネットワークに参画し、緊急大動脈重点病院となっている。当院には放射線科医を主体としたInterventional Radiology Centerがあり循環器疾患緊急症例の診断・治療に迅速に対応可能である。昭和40年代から不整脈外科が行われており、植え込み型除細動器やペースメーカー植え込み症例は年間150例を超える。特に後天性弁膜症に合併する心房細動に対する外科治療症例は全国でも抜きんでている。 |
症例数 |
定時手術は月曜から金曜まで行い、緊急手術は随時対応している。過去5年間の年間心臓血管手術数は450例前後 ★冠動脈外科=冠動脈バイパス術(CABG)は年間平均120例。長期開存率の高い動脈グラフト(内胸動脈・右胃大網動脈・橈骨動脈)による完全血行再建を前提とした手術を行っている。97年から体外循環を使用しない心拍動下バイパス術(OPCAB)を開始し、現在CABG単独症例はすべてOPCABで行っている。80歳以上の高齢者や様々な合併症を持つ重症例もOPCABで安全に手術を行っている。冠動脈疾患を合併する他疾患手術症例に対して、同時手術としてOPCABを行い、好成績を得ている。急性心筋梗塞・不安定狭心症に対する緊急手術例においても原則としてOPCABを行い、その成績は良好である。04年からの5年間で手術死亡は0である。また、小児川崎病冠動脈病変に対する内胸動脈を使用した冠動脈バイパス術を、これまでに30例以上経験しているのも特徴である ★後天性弁膜症=年間手術症例は過去5年間で平均60例。僧帽弁閉鎖不全症に対しては、原則として自己弁形成術を行っており人工弁置換術症例は少ない。高齢者であっても必要なら積極的に手術を施行している。僧帽弁膜症に合併する慢性心房細動に対しては、同時に心房細動根治治療を行っている ★大血管・末梢血管=急性解離を含む胸部大動脈瘤は年間約30例、腹部大動脈瘤も30例である。緊急手術の成績は術前にショック状態であったものを除いて全例生存している。放射線科と連携し、カテーテルによるステントグラフト内挿術を胸部・腹部の大動脈瘤に対して行っている。最近では緊急例に対してもステントグラフト挿入術を行い、成績は良好である。当院再生医療科が積極的に糖尿病に合併する重症虚血肢に対する骨髄幹細胞移植による再生医療を行っていることから、下肢動脈慢性閉塞に対する自家静脈を用いた足関節レベルへのバイパスを必要とする症例が増加している ★先天性心疾患=先天性心疾患は心房中隔欠損症、心室中隔欠損症から新生児の複雑心奇形まで、年間症例数は約30例である ★植え込み型除細動器・ペースメーカ=除細動器・ペースメーカ植え込み数は全国でも有数である。年間平均180例の植え込みを行っている。循環器内科と協力して新しい心不全治療として両心室ペーシングに積極的に取り組んでいる ★補助人工心臓=開心術後の人工心肺離脱困難例、心不全が遷延する例、急性心筋梗塞後のショックなどの重症心不全に対しては、循環器内科・麻酔科の協力を得て補助人工心臓を用いた積極的な心不全治療に取り組んでいる。 |
医療設備 |
人工心肺装置、補助人工心臓、IABP、PCPS、術中経食道心エコー、多極心外膜マッピングシステム、MRI、マルチスライスCTなど。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ×
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
形成外科・美容外科
分野 |
形成外科 |
|---|---|
特色 |
"わが国における形成外科診療の草分けの一つである。とくに高度救命救急センター、頭頸部外科、皮膚科などとの共同手術が多く、顔面・四肢外傷、先天異常、広範囲熱傷再建、悪性腫瘍切除後再建(乳房再建など)、ケロイド・傷跡の治療、美容外科手術後遺症とくに顔面や乳房の異物、褥瘡や下肢の潰瘍・壊疽に対する再生治療と手術などに世界的業績が多い。美容外科の手術やレーザー・光線治療を駆使した美容医療は、研究も含め活発である。海外からの留学生や見学者の訪問も多い。 " |
症例数 |
年間の外来患者総数は約20,000人。初診患者数は約3,000人。年間手術件数は約1,200件である。小児などのレーザー治療は、必要に応じて全身麻酔で、日帰りで行っている。得意な分野は以下の9領域 ★熱傷・瘢痕拘縮再建=元々広範囲熱傷の救命後の再建を多く経験したため、熱傷後遺症の分野に強い。とくに各種の皮弁を駆使した低侵襲の手術は海外医師の見学が引きを切らない ★ケロイド・傷跡治療=放射線治療併用手術やレーザー照射を含むケロイド治療は世界をリードしている。傷跡の治療には美容医療的手法を併用し、好結果を得ている ★先天異常=唇裂の形成は独自の方法を用い、手術跡が目立たない手術を行う。小耳症は、できるだけ就学前後に肋軟骨を使った形成手術を行う。その他の先天異常も、手術時期に見合った形成手術を行う ★癌手術後の再建手術=皮膚癌や頭頸部癌の再建は言うに及ばず、乳房再建も侵襲の少ない方法で通常手術として行っている ★足の壊疽、慢性下腿潰瘍=原因を十分に検査した上で、必要であれば手術を行う。原因によっては再生医療科との共同で治療が行われる ★美容外科後遺症とくに異物=美容外科手術の後遺症や注入異物による後遺症の診断と治療ではわが国の先端を走っており、悩める患者様は全国および外国からも来診される ★豊胸術後乳房再建、陥没乳頭=豊胸術後障害の自家組織による乳房再建と陥没乳頭の形成では、独自の術式や固定具を用い好結果を得ている ★レーザー・光治療=アンチエイジングはもちろんのこと、血管腫・ケロイド・先天性母斑の治療などを積極的に行っている ★メイクアップセラピー=かづきれいこ非常勤講師によるリハビリメイクを手術後の患者様を中心に行っており、既に10年近くの歴史を有する ★詳細は日本医科大学付属病院のホームページ「形成外科・美容外科」を参照して下さい。形成外科の対象疾患と手術法、美容医療・レーザー治療や美容外科に関する詳細な説明が閲覧できます。また、主な関連施設は以下の通り。日本医科大学武藏小杉病院(川崎市)、日本医科大学千葉北総病院(千葉県印旛郡)、会津中央病院(福島県)、北村山公立病院(山形県東根市)、東戸塚記念病院(横浜市)、博慈会記念総合病院(東京都足立区)、大浜第1病院(沖縄県那覇市)。 |
医療設備 |
超音波診断装置、各種レーザー・光機器、MDCT、内視鏡装置、皮膚還流圧測定器などを備えている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
小児科
分野 |
小児医療 |
|---|---|
特色 |
本院は東京のほぼ中心に位置する文京区にあり、区名のとおり学校や病院、公園などが多く、都内でも最も静かな環境にある。特に病院の周囲には緑が多く、四季の移り変わりは私たちに心の安らぎを与えてくれる。 明治43年に開院して以来、大学の本拠地として大学病院にふさわしい高度な医療設備、最高のスタッフを揃え「よいチームワークで患者さん中心の理想的な病院づくり」を目標として、先端医療技術と地域医療に幅広く貢献している。 厚生省許可第1号として、救命救急センターを設置し、93年4月に高度救命救急センター、同年12月に特定機能病院、08年2月にはがん診療拠点病院の指定を受け、地域医療機関との診療連携を促進するために、高度医療の充実、教育・研究面での実績を積んでいる。小児科では、外来は一般外来、育児相談、専門外来に加えて、遺伝診療外来、セカンドオピニオン外来、頭痛外来を行っている。各診療グループに分かれてはいるが、グループ間はもとより他科とも連携し、各臓器に偏ることなく全人的医療と患者様の立場に立ったていねいな診療を行うよう心がけている。大学としての高度先進医療から地域医療まで、幅広い医療活動を展開している。また各診療グループは、最新の情報を絶えず入手しながらエビデンス(根拠)に基づく治療を提供している。スタッフ全員が指導医・専門医。 |
症例数 |
★血液・腫瘍=ほとんどすべての小児血液疾患(再生不良性貧血・鉄欠乏性貧血・溶血性貧血・特発性血小板減少性紫斑病・血友病など)および小児がん疾患(白血病・リンパ腫・神経芽腫・ウィルムス腫瘍・ユーイング腫瘍・横紋筋肉腫など)に対して診療を行っている。特に白血病・リンパ腫に対しては日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)および東京小児がん研究会(TCCSG)に所属し、絶えず全国の専門医と情報交換しながら多施設で統一されたプロトコールにより治療している。神経芽腫や横紋筋肉腫、その他の固形腫瘍においても、各々の疾患に対する研究会に所属し治療をしている。常時10人前後の悪性腫瘍患児が入院しており、訪問学級も整備されて退院後の復学も円滑に行われるように配慮している。治療に際しては、抗腫瘍剤による心機能の低下や免疫能の低下について、客観的な評価を行いながら長期予後の改善を目指している。現在、当科は小児がん長期フォローアップ認定施設となっており、治療後の後遺症や生活の質(Quality of Life:QOL)の改善に取り組んでいる。悪性腫瘍以外にも再生不良性貧血の免疫療法など、小児血液疾患全般の診断・治療について、万全の体制で臨んでいる ★循環器=先天性および後天性の心疾患患者の診断・治療を行っている。先天性心疾患で手術が必要な場合には、当院心臓血管外科において行っている。また、後天性心疾患としては、主に川崎病の冠動脈後遺症を有する患者の診断および治療を行っている。特に、巨大冠動脈瘤を有する患者の診断においては、形態的な診断のみならず機能的診断を行い、その上で内科的、外科的治療を行っている。冠動脈バイパス術およびその際に適応となれば巨大瘤の縫縮術を当院心臓血管外科にて行っており、術後の成績は大変良好である。心臓カテーテル・血管造影検査はカテーテル治療を含め、年間約100例を行っている。カテーテル治療は主に肺動脈弁、大動脈弁、末梢肺動脈に行い、川崎病後の冠動脈狭窄部の形成術、冠動脈内血栓溶解術も施行している。なお、不整脈のカテーテル治療は当院循環器内科に依頼し施行している。さらに、年間約3万人の小・中・高の学童・生徒の学校心臓検診に携わっている ★内分泌・代謝=小児・思春期1型および2型糖尿病、肥満、メタボリックシンドロームを中心とした代謝疾患、低身長症を含む下垂体疾患、甲状腺疾患、副腎疾患、性腺疾患などの内分泌疾患全般について診断・治療を行っている。特に糖尿病に関しては、日本糖尿病学会認定教育施設であり、毎年、小児糖尿病サマーキャンプを実施している。糖尿病・肥満の患者数は100人を超える。また、成長ホルモン治療中の低身長児も100人に及ぶ ★アレルギー・免疫・膠原病=小児科としては全国でもきわめて数少ないリウマチ専門医が3人おり、膠原病をはじめとする各種自己免疫疾患の診療研究を行っている。そのため、リウマチ専門医でなければ使用することのできない生物学的製剤による最新の治療も、積極的に行っている。若年性特発性関節炎(若年性関節リウマチ)、全身性エリテマトーデス、リウマチ熱、皮膚筋炎、シェーグレン症候群、血管炎症候群などを主な対象としている。また、リウマチ性疾患としての側面を持つ慢性疲労症候群の診断治療にも力を入れており、われわれが発見した慢性疲労症候群に特異的な自己抗体の検査法を導入している。アレルギー疾患としては、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなどについて診療を行っている。抗ロイコトリエン拮抗薬、ステロイド吸入薬、エピネフリン自己注射薬などの最新の治療法を積極的に取り入れている。免疫疾患としては先天性免疫不全症候群や、近年注目されている自己炎症疾患について診断治療を行っている ★呼吸器=気管支喘息、呼吸器感染症、先天性呼吸器疾患、睡眠時無呼吸症候群など、小児の呼吸器疾患全般を扱っている。極小未熟児や先天性心疾患を有する乳幼児に重篤な肺炎や細気管支炎をおこすRSウイルス感染症に対し、モノクローナル抗体製剤(シナジス)を用いた予防治療を行っている ★神経=てんかん、熱性けいれんを含むけいれん性疾患を中心に、各種小児神経疾患に対し、脳波、CT、MRI、SPECTなどを用いて診断・治療を行っている(要予約)。また、臨床心理士により、発達障害に対しては知能テスト、心理的問題に対しては心理カウンセリングを行っている(要予約)。筋疾患についても必要に応じ筋生検による診断も行っている。他医療機関や保健所からの紹介を受けており、また紹介がなくても心配な症状に対し相談にのっている。外来、入院で新生児から思春期までの症例をフォローしており、必要に応じて他医療機関や、訓練のための通所施設への紹介も行っている。頭痛外来:日本の成人約40%は慢性的な頭痛があり、特に生活に支障をきたす片頭痛は8%、約800万人の方が悩まされていると報告されている。小児の頭痛は、外国の調査では片頭痛が約7%、緊張型頭痛が約13%であり、慢性頭痛で医療機関を受診する小児の半数以上が片頭痛であるとの報告もある。頭痛は小児科一般外来でもよくみられる症状ではあるが原因は多岐にわたっており、一般外来の診療時間の枠内で、頭痛に焦点を当てた十分な問診、検査、診察を行うことには限界がある。頭痛外来では、小児の慢性頭痛の診断を行い、頭痛の対処方法を見つけるため、詳細な問診に加え、頭部MRIやMRA、脳波、採血、起立負荷試験などの検査を行うほか、患児やその家族に頭痛記録(頭痛日記)を付けてもらい、患児の頭痛のパターン解明や薬剤の効果判定を行っている(要予約) ★腎臓=学校検尿で異常を指摘された方への精密検査を専門的に、毎年150人程度実施している。腎生検は年間40例以上を実施し、すでに2,000例を超えている。IgA腎症には扁桃摘出+ステロイドパルス療法を実施し、血尿・蛋白尿の陰性化を目指している。腎炎(ループス腎炎)・混合性結合組織病(MCTD)・強皮症など小児期発症のリウマチ・膠原病に伴う腎疾患の治療・管理のために通院される方も多い ★遺伝相談=当付属病院には遺伝診療科が設けられ、小児科医(右田准教授、浅野非常勤講師など)も参画している。ここでは遺伝の問題について悩んでいる方、ご家族やご本人が遺伝病の可能性を主治医に告げられている方の遺伝カウンセリング、遺伝病の診断を行っている。この外来では、臨床遺伝専門医と看護師がチームとなって病気や治療の最新の情報を提供し、遺伝に関する説明やカウンセリングを行っている。必要に応じて内外の研究者とも協力し、遺伝子検査や診断を行い、来談者の意志決定の補助を行っている。 |
医療設備 |
小児病床総数44床、乳児室12床。特定機能病院および地域がん診療拠点病院に指定された大学病院であり先進的な設備は整えられている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
眼科
分野 |
眼科 |
|---|---|
特色 |
多様な眼疾患に対して、それぞれ専門のスタッフによる診療を行っている。特に、近年増加している加齢黄斑変性に対し、血管新生阻害薬の投与やPDT(光線力学療法)など、積極的な治療を行っている。また、全身疾患に関連した眼疾患や、眼科受診者で全身的な精査や治療が必要な場合に総合病院の特性を生かし、他科の専門医と良好な連携をとっている。さらに近隣からの紹介患者も多く、地域に密着した医療を行っている。 |
症例数 |
10年度の初診患者数は5,495人、延べ患者数は43,375人、手術件数は約1,200件 ★角膜外来では、様々な角膜変性症や続発性の角膜混濁などに対して、診断と治療を行っている。特に角膜移植ではアメリカのアイバンクからの輸入角膜を用い、行っている。また、難治性の角膜上皮障害では血清点眼の投与で良好な治療効果が得られている ★ドライアイ外来では、角膜外来の一部門として、主に慢性的なオキュラーサーフェス(眼表面)の疾患に対して診療を行っている。通常のドライアイのみならず、アレルギー性結膜炎の合併例、重症のシェーグレン症候群や骨髄移植後の慢性GVHD、薬剤性粘膜皮膚症候群のスティーブンスジョンソン症候群、また一般の治療では改善しない眼精疲労、眼瞼けいれんの合併症例など幅広いドライアイとその関連疾患に対し、個々の症例に応じた診断、治療を行っている ★白内障手術は年間約900件で、超音波手術が99%、水晶体嚢外摘出術や水晶体嚢内摘出術が1%であった。眼内レンズはほぼ全例に挿入されており、アクリル素材の折りたたみ眼内レンズを使用している。高橋主任教授をはじめ、すべてのスタッフが白内障手術を行い、全例で安定した術後成績を得ている。通常の白内障手術以外にも、無水晶体眼、眼内レンズの偏位・脱臼、眼内レンズの混濁に対しても、適切かつ安全に眼内レンズの二次挿入や交換を行い、良好な視機能が得られている ★網膜硝子体手術は年間約200件行っている。網膜剥離に対しては、経強膜的網膜剥離症手術のほかに、重症例や特殊例に対しては硝子体手術で対応している。特に緊急性を要する例に対しては緊急入院の上、直ちに手術を行う体制を整備している。黄斑円孔、網膜前膜に対しても3次元画像解析などを併用した検査・診断を行い、硝子体手術で対応している。糖尿病網膜症については、糖尿病内科医、透析医との密な連携を図りながら、レーザー光凝固治療や硝子体手術を行っている ★眼炎症外来は、ぶどう膜炎、強角膜炎、視神経炎といった眼炎症疾患の診療を行っている。年間約150例の初診患者があり、三大ぶどう膜炎とされるサルコイドーシス、ベーチェット病、原田病に加え、強膜炎が特に多い。眼炎症の背景に隠れている全身性疾患について、初診時に徹底して精査している。病型と重症度に応じて、ステロイドと免疫抑制剤の点眼や内服、トリアムシノロンの眼局所注射、新しい生物学的製剤の点滴を使い分け、良好な治療成績を得ている。ぶどう膜炎に続発した白内障の手術も多い。必要に応じて外科的な治療も行っている ★斜視弱視外来は、乳児から成人まで斜視弱視の診断および訓練、手術適応の決定と術後管理を視能訓練士との緊密な連携のもとに行っている。小児眼科的要素が強い外来であるが、大学病院ならではの、外傷、中枢神経系異常、代謝異常等による神経眼科疾患への診療も行っている ★緑内障外来は、個々の病型や進行度に応じて各種薬物治療、レーザー治療、さらに手術も行っている。 |
医療設備 |
各種視野計、前眼部・後眼部超音波解析装置、角膜形状解析装置、各種レーザー凝固装置、蛍光眼底カメラ、ICG眼底カメラなど。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
血液内科
分野 |
血液内科 |
|---|---|
特色 |
急性白血病、慢性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群などの造血器悪性腫瘍、再生不良性貧血、溶血性貧血、巨赤芽球性貧血、鉄欠乏性貧血などの各種貧血症、特発性血小板減少性紫斑病、血栓性血小板減少性紫斑病、播種性血管内凝固症候群などの出血性疾患など血液疾患全般を診療対象としている。悪性、良性にかかわらず原則として病名を告知し、検査結果、治療方針などすべてわかりやすく説明することを診療の基本としている。病名告知に関する質問用紙、病状説明に用いる説明用紙、治療方針決定に関するインフォームド・コンセント用紙などを整備して用いている。 |
症例数 |
年間の入院患者数は約230例であり、その内訳は急性白血病約100例、悪性リンパ腫約40例、骨髄異形成症候群約30例、その他の造血器悪性腫瘍約30例、各種貧血症約15例、血小板減少症約5例などである。急性白血病、悪性リンパ腫などの造血器悪性腫瘍は、移植例を除いて軽快後可能な限り外来治療としており、また軽症患者は終始できるだけ外来で診療する方針を採っている。さらに、造血器悪性腫瘍以外の疾患は外来診療のみの場合が多いため、診療対象となる年間の患者数はこの数字をはるかに上回る ★治療は国内のみならず、国際的にもその時点における最新の診断技術と治療法を適用している。急性白血病、悪性リンパ腫、慢性白血病、多発性骨髄腫など造血器悪性腫瘍に対する化学療法プロトコールの臨床成績に関し、寛解率、生存期間などの観点から数年ごとに蓄積されたデータを解析しており、常にその時点における国内および国外の最高水準を維持している。急性白血病は年齢、病型により異なった化学療法プロトコールを採用しており、寛解到達後適応のある例では末梢血幹細胞移植、骨髄移植等の造血幹細胞移植を行っている。悪性リンパ腫でも病型、病期、年齢により治療法が異なり、抗体療法としてリツキシマブを用いたR-CHOP療法を中心とした化学療法を主体に治療し、放射線療法も併用している。また、適応を決めて化学療法後末梢血幹細胞移植を行っている。すなわち、診断時に予後因子を検討し、予後不良例では第一寛解期に自己末梢血幹細胞移植、あるいは高度悪性例では同胞からの同種幹細胞移植を考慮するようにしている。また再発例では可能な限り自己末梢血幹細胞移植を行うようにしている。もちろんこれらの治療を行うに当たっては前述のように病名を告知した上で選択しうる治療法を説明し、インフォームド・コンセントを得ることを前提としている。一方、造血器悪性腫瘍の治療に際しては、症例ごとにQOL(生活の質)を考慮して経口少量療法のみ、あるいは無治療とすることもある ★造血幹細胞移植に関しては臍帯血移植を積極的に行っており、さらに「ミニ移植」により高齢者あるいは臓器障害のある例にも移植を拡げている ★慢性骨髄性白血病は、若年者で同胞からの造血幹細胞移植を希望する場合以外はイマチニブ、ニロチニブ、ダサチニブなどチロシンキナーゼ阻害薬を用いる。高齢者などの限られた例では、ヒドロキシウレアで治療することもある ★重症再生不良性貧血に対しては造血幹細胞移植あるいは免疫抑制療法を行っており、良好な治療成績が得られている ★骨髄異形成症候群に対しては、患者のQOLに配慮した治療法を選択することを第一としている。予後良好群では原則として無治療で経過観察とするか、あるいは必要に応じて輸血、蛋白同化ホルモン内服、免疫抑制療法等を行い、予後不良群では、アザシチジン、レナリドミド、化学療法等を施行する。若年者では造血幹細胞移植を選択する場合もある ★病棟では日本血液学会指導医および専門医の資格を持つスタッフのもとに常勤医および研修医が複数のグループを作り、血液疾患の治療に豊富な経験を持つ看護師、その他のコメディカル・スタッフとともに緊密なチーム医療を行っている。さらに毎週1回の部長(教授)回診、血液内科全体の症例検討会、病棟ごとの症例検討会を行っている。 |
医療設備 |
完全無菌ユニット、準無菌室、全自動血球成分分離装置(末梢血幹細胞採取用)など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
リウマチ科
分野 |
リウマチ・膠原病内科 |
|---|---|
特色 |
主に関節リウマチを中心に、膠原病などのリウマチ性疾患の診療を行っている。生物学的製剤をはじめ最新の薬物治療を行うとともに、リハビリテーション、装具療法を組み合わせて、より高いQOL(生活の質)を目指している。常勤医は整形外科専門医であり、手術の必要な患者には適切な時期に手術を行う体制をとっている。 |
症例数 |
現在当科通院中の患者さんは約1,000人である。薬物治療はメトトレキサート、タクロリムス、レフルノミドなどを駆使して患者のコントロールを目指す。生物学的製剤は関節リウマチや乾癬性関節炎に対して約300人の導入実績があり、当科では合併症のチェックを十分に行い、関連各科と連携を行って安全第一に施行している。 |
医療設備 |
総合大学なので、X線、CT、MRI、PET、RI、各種内視鏡、超音波などの検査施設、ICU、CCUなどの検査施設も完備。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ×
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
神経内科
分野 |
神経内科 |
|---|---|
特色 |
神経疾患、特に脳血管障害(脳卒中)の急性期から慢性期、再発予防に関して、スタッフが一丸となり最先端の診断法、治療法を取り入れ診療にあたっている。 |
症例数 |
外来患者数は1日平均140人(うち新患12人)、入院患者ベッド数は約80、入院患者数は年間約960人(うち脳梗塞患者約400人)である。病棟回診(片山教授、桂准教授、山崎准教授)を週2回、カンファレンスを週1回行い、治療方針の決定にはスタッフ全員があたる。外来に関して初診は予約なしで可。ただし、頭痛外来、物忘れ外来、顔面眼瞼けいれん外来などの特殊外来は神経内科外来に予約要 ★脳血管障害=05年5月より脳卒中専門ユニット(Stroke Care Unit : SCU)を設立し、脳卒中専門医である上田講師、三品講師、大久保講師が中心となり、救急車の搬送を積極的に受け入れて、脳卒中の治療を専門的に行っている。CT、MRI、3DCTおよび潅流画像を用いて病態を把握しながら治療を行っている。また、発症3時間以内の脳梗塞症例に対して血栓溶解薬rt-PA(アルテプラーゼ)の使用が可能な適応患者に積極的に使用して、治療成果をあげている。毎年20症例を超える症例で安全に使用している。さらに血管内治療も実施している ★頭痛=一般外来、頭痛外来(臼田講師)において、専門医が日常生活の指導も含め、症例ごとに細やかな治療を行っている ★認知症=MRI、SPECTなどを駆使し、診断、病態把握を行って、診療にあたっている。また、神経心理検査士による詳細な知的機能の評価を基に、治療方針を決定することが可能である。特に物忘れ外来担当医(山崎准教授、石渡病院講師)は軽症の認知機能障害および前頭側頭型痴呆などアルツハイマー以外の特殊な診断にも力を入れている ★パーキンソン病=永山講師を中心に未治療パーキンソン病の症例に対しては、治療当初より長期展望に基づき患者さんのQOL(生活の質)を維持できるように細やかな薬剤調整を行っている。また、治療が長期にわたり、薬剤効果の減弱、効果時間の短縮が見られるようになった症例に関しても、入院の上、L-DOPA(Lドーパ)血中濃度の経時的測定などを行い、個々の症例に応じた適切な薬剤調整を行っている ★自己免疫性ニューロパチー=山崎准教授、酒巻病院講師を中心にギラン・バレー症候群に代表されるこれらの疾患については、IVIg(静注免疫グロブリン)療法を実施しているが、その他腎臓内科と共同で血漿交換、免疫吸着などの治療法を行う体制もあり、患者さんの早期回復に大きな効果をあげている ★眼瞼・顔面けいれん=眼瞼顔面けいれん外来(永山講師、有井孝子非常勤講師)においてボツリヌス毒素の局所注射を行い、治療効果をあげている ★脊髄小脳変性症=遺伝性脊髄小脳変性症に対しては、患者さんの希望があれば遺伝子診断が可能であり、詳細な説明の上、同意を得た場合に施行している。また、治療にあたっては、TRH(向下垂体ホルモン)ないしはその誘導体による治療を行うとともに退院後もリハビリテーションの行える環境づくりを積極的に進めている ★運動ニューロン疾患=電気生理検査により詳細な病態把握を行うとともに、多発性運動ニューロパチーなど効果的な治療が期待できる症例にはIVIg療法を行っている。また、ケースワーカーの協力のもと、地域のかかりつけ医と連絡を取り、在宅看護が可能な症例は積極的に在宅での治療を目指して入院治療を行う ★多発性硬化症=初発例に対しては誘発電位、MRIなどにより早期診断を目指している。また、慢性期症例にはβインターフェロンによる再発予防療法を積極的に進め効果をあげている ★重症筋無力症=胸腺摘出術を胸部外科と協力し積極的に進め、術前・術後管理も含めた長期の治療計画に基づきステロイド、免疫抑制剤を使用、良好な成績を得ている ★筋疾患=筋病理を専門としたスタッフ(山崎准教授)の指導の下、詳細な診断を行うとともに、炎症性筋疾患についても多くの経験を有している ★内科疾患に伴う神経疾患=膠原病に伴う神経疾患については腎臓内科の協力のもと、全身管理を含めた治療を積極的に推し進めている。 |
医療設備 |
脳卒中専門ユニット(SCU)、MRI・A、CT、3DCT、SPECT、PET。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ×
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
脳神経外科
分野 |
脳神経外科 |
|---|---|
特色 |
当教室の最大の特色は、下垂体腫瘍を中心とする間脳下垂体疾患の診断と治療を中核としていることにある。下垂体腫瘍に対する経蝶形骨手術(経鼻手術)は年間150例を超え、全例最新機器を用いた内視鏡下に行っている点が特徴である。寺本教授の経鼻手術の経験例は既に2,500例強とわが国で最も多く、世界歴代5位を超えようとしている。もう一つの特徴は単なる医療の実践にとどまらず、常に臨床・基礎医学の最新知見を取り入れながら、この分野のリーダーとして安全で確実な手術法や機器の開発を打ち出していることである。日本医大には4つの付属病院があり、そのすべてに脳神経外科が設置されているが、これを1教室で運営し各病院の情報を共有しながら相互に専門性を高めている。そのため当教室の医師は、下垂体外科のみならず、それぞれの分野で4病院全体をカバーしながら本邦屈指の外科医たらんと精進している点も特徴としてあげられる。即ち、特殊な手術が発生すると、4つの付属病院から専門としている医師達がチームを組んで集まるという仕組みをとっている。 |
症例数 |
08年から10年にかけての平均的な年間手術件数は約515件であり、下垂体部腫瘍165件(一部開頭手術を含む)、その他の脳腫瘍80件、頭部外傷45件、脳血管障害75件、脊椎・脊髄疾患90件、その他60件である ★下垂体腫瘍=脳ドックなどで偶然発見された例は、視神経を圧迫している場合のみ手術、その他は経過観察とする。視野障害や内分泌症候のある下垂体腺腫はプロラクチン産生腺腫を除いて手術を行う。手術は基本的にすべて侵襲性の低い内視鏡下の経鼻手術で行っている。この手術法を用いると、右の鼻の奥の粘膜をわずかに切るだけで腫瘍に到達でき、大きな腫瘍でも直接観察しながら安全に摘出できる。全摘出率は85%と従来の顕微鏡手術を大きく凌駕する。入院期間は2週間であり、手術の翌日からは病棟内歩行ができる。主な合併症は、鼻出血、髄液鼻漏、尿崩症、術後腫瘍内出血であり、すべてを合計した合併症率は2.5%である。しかし、寺本教授の経験例2,500余例を通じて、最終的に重篤な後遺症を残した例や手術死亡が1例もない点は、他の施設では見られない最大の特徴である。日本医大は当教室以外にも臨床・基礎医学各科に下垂体関連の研究をしている医師が特別多く、毎月内分泌カンファレンスを行っており、集学的な治療ができる点も一般病院と異なる点である。担当医師は、寺本教授、田原病院講師、石井病院講師 ★悪性脳腫瘍=手術に関しては、山口講師が最新のナビゲーションシステムと術中モニタリング・蛍光診断を駆使して、摘出率を合併症の出ないぎりぎりまで求めて成績を上げている。現在注目されている覚醒下手術もいち早く取り入れ、麻酔医や技術者もその実施に習熟している。術後の化学療法については当教室独自のプロトコールに基づき、吉田准教授が専門的な見地から長期的に責任を持って治療に当たっている ★脳室内病変=従来大きな手術が必要であった脳深部の腫瘍に対して、最近では神経内視鏡を用いて、極めて低侵襲に行えるようになった。また、水頭症に対しても内視鏡手術により簡便に治療できる。これらは喜多村准教授が担当しており、本邦ではトップクラスの実績を誇っている ★脊椎・脊髄疾患=戸田講師が担当しており、週1例のペースで主に頸椎の外傷や変性疾患を手術している。常に安全かつ確実な手術をモットーとしており、術後のリハビリ病院への紹介も親身に行っている ★脳血管障害=日本医大では急性期の超重症例は救命救急センターの脳外科医が手術を行うため、当脳外科では村井病院講師が血管吻合術を用いた巨大脳動脈瘤やモヤモヤ病などの難易度の高い手術を行っている。 |
医療設備 |
3テスラMRIをはじめMRIが5台、CT 6台、最新の内視鏡手術設備、手術用顕微鏡、ナビゲーション装置、SRS放射線装置など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
老年内科
分野 |
老年科 |
|---|---|
特色 |
高齢者は数多くの疾患を持っており、このような高齢患者に適切に対応していくのには従来の内科における臓器中心、疾患別の医療システムでは不十分である。そこで、当科では高齢者の病態生理に精通した老年病専門医が総合的に高齢患者さんを診察し、患者さん全体の生活の質(QOL)を高めるための治療には何がベストであるかを見極めることに主力をおいている。それはどこまでを当科が責任を持って診療し、どこを他科の専門医に診てもらうかということを判断することである。このように当科の診療は、多くの他科の専門医との連携のもとに、高齢者の全体像を把握して診療していくところにその特色がある。 |
症例数 |
年間の外来数は約15,000人、入院患者数は約400人 ★診療する疾患は内科の各領域に広くまたがるが、糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満などの生活習慣病や各種動脈硬化性疾患(脳血管障害、虚血性心疾患、末梢動脈硬化症)、さらに認知症の診断・治療が中心。特に糖尿病は専門領域として診療を行っており、糖尿病専門医による糖尿病外来、糖尿病教室および教育入院(1週間コース、2週間コース)を実施 ★他の特殊外来として動脈硬化外来(非侵襲的な検査により全身の動脈硬化の程度を定量的に評価し、適切な治療法を選択する)、高血圧症外来(24時間携帯型血圧計による血圧日内変動の解析などを行い、適切な薬剤と投与量を設定する)、肥満外来(専属栄養士によるきめ細かな食事療法指導を中心に減量を図る)、認知症外来(軽症例は診断が中心となるが、重度の方は関連病院の認知症専門病棟での加療となる ★また保健・福祉との連携方法などの説明を含めた介護上の種々の相談も受けている)がある。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
内分泌外科
分野 |
乳腺・内分泌外科 |
|---|---|
特色 |
当施設では78年より甲状腺特殊外来を開設し、甲状腺、副甲状腺、副腎疾患を中心に専門的見地より診断と治療を行っており、11年5月までで新患者数は8,000例以上に及ぶ。特に甲状腺、副甲状腺疾患に関しては98年3月、国内外に先駆け低侵襲性と美容面ならびにその後のQOL(生活の質)を重視した内視鏡手術を開発した。11年5月現在で症例数は530例を超え、国内外を通じて症例数は最も多く、その有用性は高く評価されている。このため全国から手術希望者や国内のみならず海外からの見学者は後を絶たない ★臨床面では、甲状腺疾患はもとより内分泌疾患全般にわたり全国から紹介を受け入れ、その治療に当たっている。当院内科はもとより、都内の内分泌専門内科より多数の患者さんの紹介を頂いている。そのため紹介元の病院とは常に連携を保ち、術後の治療は患者さんの通院しやすい環境の構築に努めている ★患者さんの治療に当たっては、病気について十分に話し合い、理解を深めていただき患者さんにとって最適な治療法を選択し、納得を頂いた上で行っている。その一環として入院前、外来にて担当医や担当看護師より入院から退院までの流れを説明する時間を設けている。これは通常の外来時間枠外で行うことで、入院前の不安をできるだけ少なくしご家族も共通の認識をもっていただけるよう努力している。入院後はクリニカルパスに基づきチームの連携を密に取り、術前術後の治療にあたっている ★また、内分泌遺伝性疾患(甲状腺髄様癌、副腎褐色細胞腫、原発性副甲状腺機能亢進症など)に対しては、本院遺伝外来と綿密な連携の下、患者さんのプライバシーに十分配慮し、心理的サポートや十分なカウセリングを行った上で遺伝子診断を行っている。 |
症例数 |
当施設で98年3月に内視鏡手術を導入してから、11年5月までの手術症例数は甲状腺手術2,035例で、内訳は良性腫瘍926例、悪性腫瘍771例、バセドウ病305例、橋本病33例である。そのうち536例の甲状腺疾患に対し、内視鏡手術を施行した。当科独特の前頸部に手術創を置かない吊り上げ法を用いた方法は、甲状腺疾患が女性に多く、常に露出された前頸部に手術創が残る通常手術と比べ、美容上のQOLを重視しており、術後のアンケート調査において極めて満足すべき結果を得ている。入退院に関してはクリニカルパスを導入している。甲状腺疾患に関して平均的には手術2日前に入院し、術後3日目に退院としているが、疾患により多少の変更はある ★良性甲状腺疾患=通常は経過観察か甲状腺ホルモン剤によるTSH抑制療法、必要に応じPEIT療法を施行している。内視鏡手術は全体の45%であり、標準手術となりつつある ★甲状腺癌=100件。組織型と術前の評価により適切な術式を選択しているが、甲状腺機能温存、副甲状腺機能温存および周囲神経の機能温存を第一に心がけている。術後10年生存率は90%を超えている ★バセドウ病=40件。手術適応は慎重に検討し、内視鏡手術の適応があれば本術式を選択している ★副甲状腺=20件。原発性および続発性とも術後の臨床症状の回復は顕著である。超音波、シンチグラフィーで術前に局在診断を正確に行い、できるだけ侵襲の少ない頸部小切によるラジオガイド下手術(2~3cmの皮膚切開)を施行している。クイックPTH測定を導入し、根治率の向上を目指している ★副腎疾患=20件。当院内分泌内科、消化器外科、放射線科と連携の下、副腎腫瘍(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫、非機能性腫瘍)の診断、手術を施行しており、内視鏡手術を第一選択としている。10年はすべての症例が内視鏡手術であった。従来法の手術では開腹しない後腹膜腔アプローチを選択しており、術後の回復は極めて早い。 |
医療設備 |
内視鏡手術機器、手術用ナビゲーションシステム、術中モバイル型ガンマカメラ装置、カラードプラ超音波装置、CT、MRI、シンチグラフィー、外来化学療法室などを備えている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
乳腺科
分野 |
乳腺・内分泌外科 |
|---|---|
特色 |
当院は08年4月より地域がん診療連携拠点病院に認定され、地域医療を担当される病院、診療所との緊密な連携を保ちながら、5大癌の一つである乳癌に対しても重点を置いて診療に当たっている。08年5月より、従来の乳腺外科(旧第一外科)と内分泌外科(旧第二外科)の乳腺部門を統合し、乳腺科外来を独立に開設した。これにより、月曜日から土曜日まで、毎日乳腺科外来を開くことが可能になった ★外来担当は上記の乳腺専門医をはじめ、乳腺疾患診療のエキスパートである乳腺病理医、放射線診断医、放射線治療医、がん専門薬剤師、乳がん看護認定看護師、がん化学療法看護認定看護師、マンモグラフィ撮影認定放射線技師、細胞診断士、緩和ケアチーム(医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー)など、乳癌診療に携わる有資格者が多数在籍し、質の高いチーム医療を実践している。女性スタッフも豊富であり、患者さんに優しい医療を心がけている。当院のスタッフは乳腺以外の疾患についても幅広い臨床経験を有しており、さらに総合病院であるために、様々な併存疾患のある患者さんにも対応が可能である ★対象として、有症状患者さん、他院からの紹介症例のほか、乳癌検診の2次精査機関として1次検診機関からの紹介患者さんの診断を行っている。初診患者さんに関し、マンモグラフィ、乳房超音波検査、さらに必要な場合は穿刺吸引細胞診(FNA)や針生検(CNB)などの検査を1日で行うことを原則としている。通常のマンモグラフィや乳房超音波検査で診断が困難な微細石灰化病変等の症例に対し、画像ガイド下マンモトーム生検で病理診断を行っている。また、手術前に乳房MDCTやMRIを用いて癌の拡がり診断を行い、乳房温存手術の適応や適切な切除範囲の決定をしている。RI・色素併用法センチネルリンパ節生検の転移検索や乳房温存手術の断端検索に関して、術中迅速病理診断を実施しており、再手術の回避も含め、良好な成績を得ている ★治療の面では、基本的に現在の標準治療を施行している。術前化学療法や乳房温存療法、併用法センチネルリンパ節生検などをはじめとする現在の標準治療を基本的に施行。乳房手術に関しては、標準的な乳房温存手術、乳房切除術に加え、鏡視下手術も施行している。乳房再建術に関しては、主に二期的再建を施行しており、当院形成外科あるいは近医への紹介で対応している。外来通院化学療法の専門部門があり、術前・術後・転移再発乳癌の患者さんに安全・快適な点滴環境を提供している。乳房手術後や骨・脳転移などに対して、放射線科と連携して放射線治療を行っている。さらに、心のケアとして、精神腫瘍医の診療を受けることができる。また、当院には東洋医学科があり、抗癌剤やホルモン剤の副作用対策として漢方薬の処方や針治療などを受けることもできる。当院の遺伝診療科では遺伝性乳癌に関するカウンセリング、遺伝子検査の相談などを担当しており、当科と密に連携をとって患者さんのニーズにお応えしている。また、病理部とタイアップし、乳腺病理医が顕微鏡画像を示しながら病理組織所見をわかりやすく解説する、ユニークな病理外来も行っている(希望者のみ)。セカンドオピニオン(紹介、被紹介)も受け付けている。詳細についてはhttp://www.hosp.nms.ac.jp/tables/index.phpを参照。 |
症例数 |
年間手術症例数は約160件で、疾患の程度にあわせた最適かつ標準治療を提供できる。ほぼクリニカルパス(最適の診療条件で標準治療を行うための病院用、患者用のスケジュール表)に沿って治療方針を立てて治療を遂行している。また、高齢化とともに種々の基礎疾患(合併症)をもった方が、そのために手術を受けられないことが多く見受けられるが、当科では、大学付属病院および特定機能病院かつ地域がん診療連携拠点病院として、総力をあげて治療に取り込めるような診療連携システムをとっており、近隣の有数の専門病院から、その総合力を求められ紹介されることも多い。その医療水準は各専門病院に比べ遜色ない。それぞれの進行度に応じた治療法を模索し、疾患の制御のみでなく、QOL(Quality of Life:生活の質)を重視した集学的治療を推進している。また、教室の伝統として、徒らに成績などの数字で惑わされることなく、患者さんが一番必要としている「満足」を十分に満たすような適格な診断および治療法の提示、セカンドオピニオンの勧めなど、全人的診療を心がけている。 |
医療設備 |
マンモグラフィ、超音波診断装置(エコー)、ステレオガイド下マンモトーム生検装置、ヘリカルCT、MRI、SPECT-CT、PETなど、大学病院として診療に必要な設備はすべて揃っている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
放射線科
分野 |
放射線科 |
|---|---|
特色 |
常勤医35人、非常勤医5人のスタッフで、あらゆるモダリティーの画像診断を行っており、読影報告書の即時発行に対応している。日本医学放射線学会専門医21人、日本核医学専門医8人、PET認定医8人、日本IVR学会専門医3人、日本放射線治療専門医2人、日本がん治療認定医1人、マンモグラフィ認定医8人と、各分野の専門医を擁しており、読影報告書の質の保持に努めている。また入院病室も有しており、IVR、放射線治療後の病棟対応も行っている。 |
症例数 |
★CT部門では、64列ならびに32列マルチスライスCT装置をはじめ、4台の診断用CT装置が稼働している。CT検査件数は年間35,000件を超え、高度救命救急センターや集中治療室に搬送されるあらゆる病態の患者様に対応すべく、365日24時間の緊急対応を行っている。また、すべてのCT検査に対して、専門医による読影報告書を即時発行することで、診断から治療に至る最良な医療の提供に加え、必要な情報を立体的な3次元CT画像として提供し、治療効果判定やインフォームド・コンセントに活用している。血管系における3次元画像も心臓の冠動脈、脳血管、大血管から末梢血管に至るまで、全身のあらゆる部位にも対応している ★MRI部門では、1.5テスラMRI装置3台および3テスラ装置1台が稼働しており、検査件数は年間で約13,000件である。通常のMRI検査の他にも、心筋症を中心とした心臓MRIや新技法を用いた胸腹部MRA(MR血管撮影)を実施している。さらには、拡散強調像を用いた全身腫瘍イメージングにも積極的に取り組んでいる ★血管造影部門ではIVRを含め、年間2,700件の血管造影が行われている。当院はIVR専門医修練施設に認定されており、「IVRセンター」において年間800件におよぶIVR診療が行われている。血管系IVRは肝癌に対する動脈塞栓術やリザーバー治療、ASOや透析シャントトラブルに対するPTA、ステント治療の件数が多い。非血管系IVRもCTガイド下生検、膿瘍ドレナージ、気管ステント、ラジオ波治療など広い領域をカバーしている。当科の特徴として、救急疾患に対するIVRが挙げられ、外傷や消化管出血に対する超選択的止血術や、静脈血栓塞栓症に対するハイブリッドIVR治療にも対応している。また閉鎖回路下抗癌剤灌流療法は、当科が独自に施行している治療であり、骨盤内腫瘍に対する高濃度抗癌剤治療を行っている ★核医学部門では、4台のガンマカメラが稼働しており、年間の検査検数は5,000件を超える。脳核医学では画像の標準化のために独自に開発した解析プログラムを用い、統計画像処理による認知症診断、脳動脈閉塞症に対する脳虚血重症度自動診断を実践している。心臓核医学では心筋梗塞や狭心症例における負荷シンチグラフィーを施行し心筋虚血の評価を行っており、CT冠動脈像との融合による心臓フュージョンイメージを作成し、詳細な心臓画像診断を行っている。また、付属病院に隣接する健診医療センターではPET-CTによる癌診断を行っており、年間4,000件に達する。うち4割は検診スクリーニングの受診者であり、早期癌の検出に努めている ★治療部門における対象疾患は脳腫瘍、頭頸部癌(咽頭癌、喉頭癌など)、胸部悪性腫瘍(肺癌、食道癌、乳癌など)、腹部・骨盤部悪性腫瘍(子宮癌、前立腺癌、肝癌など)、血液疾患(白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫など)、良性疾患(ケロイド、甲状腺眼症、血管腫など)、緩和療法(脳転移、骨転移に対する症状緩和)と多岐にわたっており、年間10,000件に達する。またヨード125のシードを利用した前立腺癌に対する小線源治療も行っている。 |
医療設備 |
MRI、CT、SPECT、SPECT-CT、PET-CT、IVRセンター、リニアック、マンモグラフィ、超音波、一般病室など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
高度救命救急センター
分野 |
救急医療 |
|---|---|
特色 |
極めて重篤な救急患者(3次救急患者)を対象に高度な救急医療を24時間体制で提供している。診療にあたっては外科学会、脳神経外科学会、外傷学会、整形外科学会、内視鏡学会、熱傷学会、脳血管内治療学会、脳卒中学会の各専門医などの資格を有する救急指導医、救急科専門医が初診から手術を含めた集中治療を行う。豊富なマンパワーと救急医療への情熱を基に、東京都第3次救急医療施設として東京消防庁からの救急患者収容要請や、2次救急病院からの救急患者さんを受け入れている。治療は院内臨床各科と密接に連携を取りつつ、初期治療から手術やICU管理まで救命救急センター専属の医師(3つのグループで構成)と看護師(約100人2交代制)が24時間体制で行っている。また、最近多発する国内外の大災害や事故に対して迅速に医師を派遣する体制が完備されている。当施設は大学や国公立病院の救急部門指導者を多数輩出している。 |
症例数 |
入院患者は心肺危機を伴う、あるいはその危険性の高い重症救急疾患に限られ、年間入室患者は約2,000~2,300人で、ほぼ全例が救急車で来院する。疾患別内訳は、脳血管障害37%、多発外傷など重症外傷34%、急性腹症13%、広範囲熱傷9%、呼吸不全9%、急性中毒4%など、あらゆる重症救急疾患である。来院時心肺停止の症例は年間約300例、そのうち生存退院は11.4%、特に脳低体温療法を導入した場合の社会復帰率は24%と、極めて優れた成績を誇っている。手術件数は年間約950件で、内訳は整形外科手術350件、開頭術300件、開腹術150件、開胸術70件、植皮術70件など。収容患者の2/3は患者発生現場からの直接搬送、残り1/3は他院からの転送である。02年からはドクターアンビュランスを運用し、東京消防庁司令室の要請により年間約500回出動し、重症患者に対して発生現場から治療を行っている。また、災害医療支援も積極的に行い、東日本大震災をはじめ、国内外の災害や大規模事故に対して多くの人材を派遣している ★外傷=中央手術室までの搬送が間に合わない超重症例では、初療室での開頭、開胸、開腹手術を行っている。重症頭部外傷に対しては、脳低体温療法を行っている ★熱傷=広範囲熱傷に対して、同種皮膚(allograft)を用いた受傷後早期植皮術と集学的治療を行い、救命率の改善をみている ★脳血管障害=脳動脈瘤のクリッピングやコイル塞栓術、脳出血に対する開頭術、および急性期脳梗塞に対するt-PA、MERCI治療など、早期治療の方針をとっている ★中毒=急性中毒の迅速分析は、法医学や公衆衛生学教室の協力のもと体制を整えている ★臓器不全=呼吸循環管理と体液管理を中心にして、肝・腎など代謝臓器不全に対する持続的血液濾過透析法(CHDF)や経皮的人工心肺補助循環装置(PCPS)、血漿交換療法などの血液浄化法を駆使した集中治療を行っている ★精神疾患合併症への対応=自殺企図者やICUにおける譫妄症例などに対して、センター専従の精神科医による診療が行われている。 |
医療設備 |
専用の初療室(3床)、集中治療室(ICU 17床)、ハイケアユニット(HCU 30床)。熱傷用空気流動ベッド3、治療用高機能体位変換ベッド3、人工呼吸器16、血液透析装置、持続的血液浄化法装置、胸腔鏡および腹腔鏡手術装置、定位脳外科手術用装置、成分輸血用血液分離装置、脳波計、聴性誘発電位検査装置、経頭蓋骨ドプラ装置、PiCCO、超音波診断装置、各種ビデオファイバースコープ、中毒薬剤分析器、呼気ガス分析器、オンライン化されたベッドサイドモニター、経皮的人工心肺補助循環装置、高気圧酸素治療設備(II類)など。 |
- セカンドオピニオン受入 /
- 初診予約 /
- 主治医指名 /
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
- 消化器内科
- 外科(消化器・一般・乳腺・移植部門)
- 呼吸器内科
- 循環器内科
- 心臓血管外科
- 形成外科・美容外科
- 小児科
- 眼科
- 血液内科
- リウマチ科
- 神経内科
- 脳神経外科
- 老年内科
- 内分泌外科
- 乳腺科
- 放射線科
- 高度救命救急センター
- 皮膚科
皮膚科
分野 |
皮膚科 |
|---|---|
特色 |
あらゆる皮膚疾患を幅広く診療している。おおよそ皮膚科領域で扱う疾患のほぼすべてを網羅し、取り扱っている。特に、悪性腫瘍(扁平上皮癌、メラノーマ、リンパ腫など)、血管炎、じんま疹、薬疹などアレルギー性疾患、乾癬、膠原病、水痘症など免疫疾患、下腿潰瘍、四肢壊疽など循環障害、ニキビ、シミ、アザ、シワ、脱毛症などの整容的疾患、および細菌・ウイルス・真菌感染症、性感染症の診断・治療に精通している。また、内科・外科・小児科などの他科との境界領域にある疾患も、他科との密接な連携のもとに積極的に診療している。130年以上の歴史と伝統を誇る「臨床に強い日本医科大学」の名に恥じない、幅広い臨床診断力と高い治療技術を有するのはもちろんのこと、あたたかく人間味のある対応を常に心がけている。また、臨床に直結した研究テーマを数多く掲げ、新しい診断・治療法を開発する努力をしている。「病診連携」「病病連携」にも力を入れ、一般病院や開業医との定期的な連絡や会合を行い、また、各種の臨床家向けの皮膚科セミナーを年数回開催するなど、紹介元となる医院・病院との連携が密になるように、鋭意努力している。 |
症例数 |
当院皮膚科の1日の平均外来患者数は約180人、平均入院患者数20人。また、年間手術件数は680件(10年度)である。当科で常時開設している専門外来には、以下のようなものがある ★アレルギー外来=アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎、じんま疹、薬疹、食物アレルギーなどのアレルギー疾患について、詳細なアレルゲン検査、診断、治療を行っている。特に薬疹や薬剤アレルギーの診断に関しては精通しており、かねてより定評がある ★真菌外来=難知性爪白癬や角質増殖型白癬、深在性真菌症の診断および治療を行っている ★水疱症外来=天疱瘡、類天疱瘡などの自己免疫性水疱症、遺伝性水疱性疾患を対象としている。血液検査、病理組織検査、免疫学的検査、遺伝子検査により迅速な診断を行い、各個人に最適の治療法を選択している ★光線外来=乾癬、リンパ腫などに対する紫外線療法(PUVA、ブロードバンドUVB、ナローバンドUVB)を行い、それぞれの疾患に対して良好な治療成績を得ている ★乾癬外来=難治性乾癬(尋常性乾癬、膿疱性乾癬、関節症性乾癬)に対し、症例に応じた外用治療、光線治療、内服治療を行っている。重症例には、新規治療薬である生物学的製剤(抗サイトカイン薬)による免疫療法を施行し、良好な治療成績を得ている ★心療皮膚科外来=ストレスが引き金になったり、増悪因子となる円形脱毛症やアトピー性皮膚炎など難治性皮膚疾患に対して、心理・精神医学的治療法を取り入れている ★美容外来=全国の大学病院皮膚科に先がけて、美容皮膚科を開設し、多くの患者さんに好評を得てきている。カウンセリングを行い、皮膚科学的な診断に基づいて治療方針を決定している。施術内容としては、ニキビ、シミ、シワ、アザ、血管拡張、瘢痕、ケロイド、多毛などに対して、各種レーザー・IPL、ケミカルピーリング、フォトダイナミックセラピー(PDT)、外用剤(ハイドロキノン、トレチノイン、活性型ビタミンC)を用いている。 |
医療設備 |
Qスイッチルビーレーザー、アレキサンドライトレーザー、ダイレーザー、ヤグレーザー、フラクショナルレーザー、炭酸ガスレーザー、エキシマライト、フラッシュランプ(IPL)、PDT装置、ロボスキンアナライザー、紫外線照射装置(UVA、ブロードバンドUVB、ナローバンドUVB)、ダーモスコピー、MRI、CT、サーモグラフィー装置 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ×
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 東京都版」(ライフ企画 2011年11月)
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
日本医科大学付属病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
日本医科大学付属病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 名医の推薦分野について
- 名医の推薦分野に掲載する情報は、ライフ企画が独自に調査、取材し、出版する書籍、「医者がすすめる専門病院」「専門医が選んだ★印ホームドクター」から転載するものです。出版時期は、それぞれの情報ごとに記載しています。全ての情報は法人としてのQLifeの見解を示すものではなく、内容を完全に保証するものではありません。
 QLife会員になると特典多数!
QLife会員になると特典多数!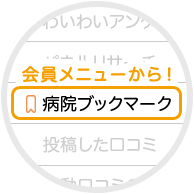

診療科目:婦人科
20代以下女性 2019年03月16日投稿
大きい病院ですので、設備はしっかりしており、24時間空いているコンビニがあるので、とても良かったです。 先生や看護師さんの数も多く、気になる人はやはりいるものの殆どが良い…続きをみる